この日何の日?
レッド・ツェッペリンのアルバム「コーダ(最終楽章)」が全米でリリースされた日
この時あなたは
0歳
無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます
1982年のコラム
お嫁さんにしたい女優ナンバーワン!竹下景子が演じたソープ嬢モモ子シリーズ
フィービー・ケイツだけじゃない「初体験 リッジモント・ハイ」は音楽も豪華
ジョージ・ハリスン「ゴーン・トロッポ」でポカポカの年越しのススメ
フィル・コリンズ「恋はあせらず」80年代に引き継がれたモータウンサウンド
ディレカン製作「さらば相棒」ARB の歌が聴きたい!ピンク映画も見たい!
多様性社会の先駆け、性差も人種もヒョイっと飛び越えたカルチャー・クラブ
もっとみる≫
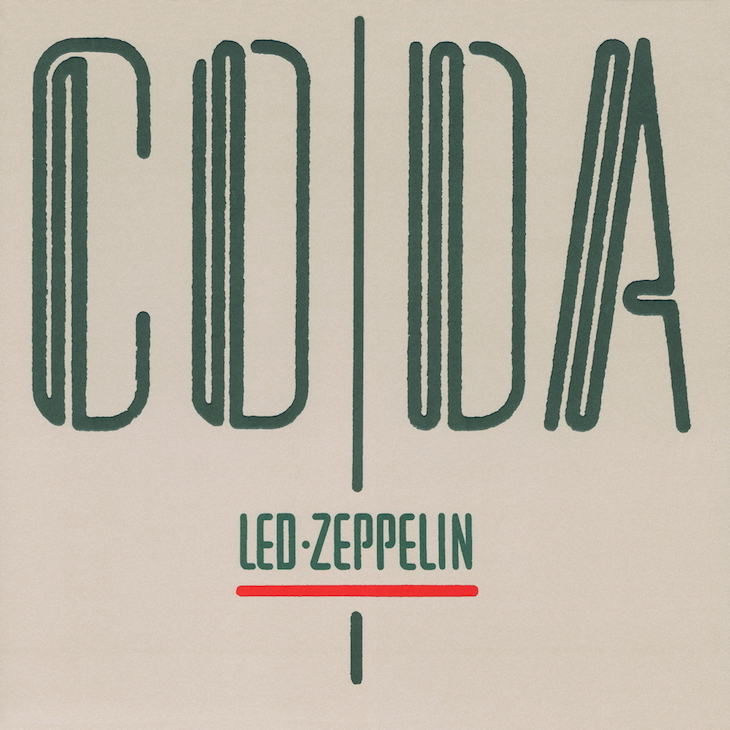
photo:Warner Music Japan
ここで触れるまでもないが、昨年末、僕たち年配の音楽ファンの話題は、クイーンの伝記的映画『ボヘミアン・ラプソディ』で一色だった。個人的には、この映画に対する日本での異常な盛り上がりに疑問と違和感しかないが、映画自体は間違いなく面白かったし、最後の約20分間のライヴエイドのシーンは、見事に1985年当時のステージを再現していたと思う。
ライヴエイドについては、当時を思い起こすと、確かにクイーンのパフォーマンスは圧巻で、少なくともウェンブリー・スタジアムのステージは、彼らの「一人勝ち」だったと言っても決して言い過ぎではない(と当時も思っていた)。
その陰で、最悪のパフォーマンスを見せたのがレッド・ツェッペリンだ。80年に解散していた彼らにとって、亡くなったジョン・ボーナム(通称ボンゾ)以外の3人が揃ってステージに上がったのは、これが解散後初めてのことだったが、その出来は誰がどう見ても「醜態」としか言いようのない酷いものだった。
そもそも、解散の意味を自分達が一番解っていたはずなのに… どうして彼らはライヴエイドに出演したのだろうか?
僕は今でもレッド・ツェッペリンが史上最強のロックバンドだと信じているが、残念ながら殆どの作品を「後追い」で聴いてきた。65年生まれの僕が、音楽的な意味で物心がついたのが70年代後半だったから、要するに「間に合わなかった」のだ。
だから、彼らが解散するまでの間に、僕がリアルタイムで聴くことができた唯一のアルバムは79年リリースの『イン・スルー・ジ・アウト・ドア』だった。でも、正直なところ、当時は何と言うか、今一つピンと来なかった。何故なら、想像していたレッド・ツェッペリンのサウンドとイメージがだいぶ違っていたからだ。そんな訳で、彼らの「新譜」を初めて心から堪能することができたのは、まだ僕が高校生だった82年リリースの『コーダ(最終楽章)』である。
このアルバムは、バンドのギタリスト兼リーダー兼プロデューサーであったジミー・ペイジが、解散後に未発表音源を集めてアルバム化したものだ。レコード会社との契約上、レッド・ツェッペリンとしてもう1枚アルバムを発表しなければならなかったらしく、苦し紛れに制作された感はあるものの、前作『イン・スルー・ジ・アウト・ドア』よりずっとハードロックっぽくて、僕が期待していたツェッペリンサウンドそのものであった。
そして、このアルバムによって改めて認識させられたのが、ツェッペリンサウンドの軸がボンゾのドラムだったこと。それ故、彼が急逝した時に解散するしかなかったという圧倒的な「事実」。そして、このアルバムの選曲とミックスダウンからは、ファンにその「事実」を納得させようというジミー・ペイジのメッセージが込められているような気がした。
中でも「オゾン・ベイビー」、「ダーリーン」、「ウェアリング・アンド・ティアリング」の3曲は、いずれも前作『イン・スルー・ジ・アウト・ドア』のアウトテイクだが、お蔵入りしたことが不思議なくらい、前作以上にツェッペリンらしいサウンドだ。それに、ボンゾのドラムの迫力と疾走感、それらを支える繊細な技術は、まさに「余人をもって代え難い」としか言いようがなかった。だからこそ、不可解だったのだ。どうして彼らはライヴエイドに出演してしまったのか?
ただ、逆説的ではあるが、ライヴエイドのパフォーマンスがあまりにも酷かったことで、かえってボンゾの存在を浮かび上がらせたというのも事実だ。それもまた哀しい話ではあるのだが…
Official Albums Chart
■In Through The Out Door(1979年9月8日 全英1位)
■Coda(1982年12月4日 全英4位)
Billboard 200
■In Through The Out Door(1979年9月15日 全米1位)
■Coda(1983年1月15日 全米6位)
2019.01.31
ライヴエイドについては、当時を思い起こすと、確かにクイーンのパフォーマンスは圧巻で、少なくともウェンブリー・スタジアムのステージは、彼らの「一人勝ち」だったと言っても決して言い過ぎではない(と当時も思っていた)。
その陰で、最悪のパフォーマンスを見せたのがレッド・ツェッペリンだ。80年に解散していた彼らにとって、亡くなったジョン・ボーナム(通称ボンゾ)以外の3人が揃ってステージに上がったのは、これが解散後初めてのことだったが、その出来は誰がどう見ても「醜態」としか言いようのない酷いものだった。
そもそも、解散の意味を自分達が一番解っていたはずなのに… どうして彼らはライヴエイドに出演したのだろうか?
僕は今でもレッド・ツェッペリンが史上最強のロックバンドだと信じているが、残念ながら殆どの作品を「後追い」で聴いてきた。65年生まれの僕が、音楽的な意味で物心がついたのが70年代後半だったから、要するに「間に合わなかった」のだ。
だから、彼らが解散するまでの間に、僕がリアルタイムで聴くことができた唯一のアルバムは79年リリースの『イン・スルー・ジ・アウト・ドア』だった。でも、正直なところ、当時は何と言うか、今一つピンと来なかった。何故なら、想像していたレッド・ツェッペリンのサウンドとイメージがだいぶ違っていたからだ。そんな訳で、彼らの「新譜」を初めて心から堪能することができたのは、まだ僕が高校生だった82年リリースの『コーダ(最終楽章)』である。
このアルバムは、バンドのギタリスト兼リーダー兼プロデューサーであったジミー・ペイジが、解散後に未発表音源を集めてアルバム化したものだ。レコード会社との契約上、レッド・ツェッペリンとしてもう1枚アルバムを発表しなければならなかったらしく、苦し紛れに制作された感はあるものの、前作『イン・スルー・ジ・アウト・ドア』よりずっとハードロックっぽくて、僕が期待していたツェッペリンサウンドそのものであった。
そして、このアルバムによって改めて認識させられたのが、ツェッペリンサウンドの軸がボンゾのドラムだったこと。それ故、彼が急逝した時に解散するしかなかったという圧倒的な「事実」。そして、このアルバムの選曲とミックスダウンからは、ファンにその「事実」を納得させようというジミー・ペイジのメッセージが込められているような気がした。
中でも「オゾン・ベイビー」、「ダーリーン」、「ウェアリング・アンド・ティアリング」の3曲は、いずれも前作『イン・スルー・ジ・アウト・ドア』のアウトテイクだが、お蔵入りしたことが不思議なくらい、前作以上にツェッペリンらしいサウンドだ。それに、ボンゾのドラムの迫力と疾走感、それらを支える繊細な技術は、まさに「余人をもって代え難い」としか言いようがなかった。だからこそ、不可解だったのだ。どうして彼らはライヴエイドに出演してしまったのか?
ただ、逆説的ではあるが、ライヴエイドのパフォーマンスがあまりにも酷かったことで、かえってボンゾの存在を浮かび上がらせたというのも事実だ。それもまた哀しい話ではあるのだが…
Official Albums Chart
■In Through The Out Door(1979年9月8日 全英1位)
■Coda(1982年12月4日 全英4位)
Billboard 200
■In Through The Out Door(1979年9月15日 全米1位)
■Coda(1983年1月15日 全米6位)
2019.01.31
Apple Music
Apple Music
Information
あなた
おすすめのボイス≫
ライブエイドのロックンロールのソロはカッコいいよ。フランジャー効きすぎがいいんだ。
2022/04/09 05:32
























