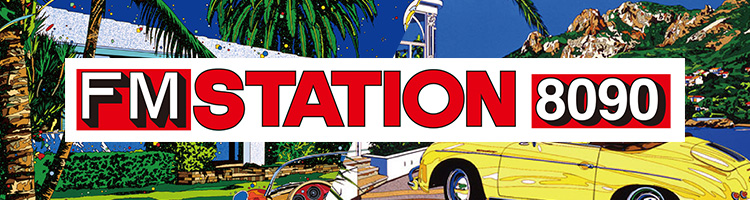この日何の日?
コンピレーションアルバム「FM STATION 8090~GOOD OLD RADIO DAYS」
「FM STATION 8090~GENIUS CLUB」発売日
「FM STATION 8090~GENIUS CLUB」発売日
この時あなたは
0歳
無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます
2023年のコラム
音楽があふれるまち渋谷!ギタリスト佐橋佳幸とSETAが届ける「うたのカレンダー」
ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース!忘れちゃいけない80年代最強のロックンロールバンド
ワム!をバカにするな!売れ過ぎて正当に評価されなかった “時代のポップアイコン”
FM STATION 8090《小林克也編》冴えわたるDJ!山下達郎「COME ALONG」再び!
アイドルから大人のシンガーへ!歌手 河合奈保子の成長は売野雅勇の歌詞があってこそ
DJ【小林克也】最新インタビュー ② 山下達郎「COME ALONG」と「ベストヒットUSA」
もっとみる≫

第1回 そのまま曲名を告げるだけではダサいからね!
80年代のラジオカルチャーは僕らに色々なことを教えてくれた。FM雑誌、エアチェック、そしてとびっきりのDJが道先案内人だった。当時、鈴木英人のイラストが表紙を飾っていたFM STAITIONとのコラボレートで、7月12日に2タイトルのシティポップオムニバスがリリースされる。そこには当時の珠玉のナンバーに加え、80年代の空気感を現代へと甦らせるDJの存在は欠くことができない。今回はリリースを記念してオムニバスCDのDJを務めた小林克也氏に当時のラジオ事情やDJとしての在り方、そして80年代に至るまでの音楽の成り立ちなど多岐にわたるテーマでお話を伺うことが出来た。
―― FM雑誌が続々と創刊し、エアチェックのカルチャーが花開いた80年代、シティポップはどのように形成されて行ったのでしょう?
小林克也(以下克也):60年代、アメリカはビートルズに荒らされて、音楽シーンも一掃されたわけですよね。ミュージシャンたちもダンスミュージックだけではなく、芸術志向が高まってくる。ポップスにインテリ層が参加するようになって、社会的なメッセージも含め、広がりを見せてきます。当時音楽を志す人たちは、そういった高い望みを持つようになります。それまで最高とされていたマイルス・デイビスなんかがやっていたモダンジャズまで少なからぬ影響を受けています。子どもたちだけがターゲットではない社会的な問題を歌にするアーティストも出てきたりして、これも音楽が広がる大きなきっかけでしたね。
そんな中でレコード会社にすごく大きな変化が訪れます。70年代にキャロル・キングの『タペストリー』というアルバムが何百万枚と売れました。そうすると何十億という売り上げになりますよね。1枚のアルバムがそれだけのお金を動かすということがわかって、レコードは確率のいいバクチだと思われるようになる。レコード会社には映画会社の資本も入って、映画からヒット曲を生み出そうとする。つまり、この時期に現在に至るまでのミュージックビジネスの下地が完璧に出来上がったということです。
アメリカのこのような流れが日本にも浸透し、さらにウォークマンやビデオという新たなツールで音楽を楽しめるようになる。シティポップの流行にはそんな時代背景がありました。
井上鑑さんがプロデュースして大ヒットした寺尾聰の『リフレクションズ』は、画期的でした。録音の方法とか、ファンキーな要素を入れるとか、独特の感性がありました。このアルバムでやっているボーカルの多重録音なんかも井上鑑がスタートさせたもので、当時はみんなが真似しました。彼の功績はすごいんです。

―― 今回の『~NIGHTTIME CITYPOP』もこの『リフレクションズ』に収録された「出航 SASURAI」から幕を開ける。克也氏のナレーションは、まさしく、この『リフレクションズ』へのオマージュ、そして寺尾聰への賞賛だと思えてならない。ちなみに今回の台本もご自身が執筆している。これが小林克也のこだわりでもある。
克也:ナレーションの台本って制限がある。だけど、もっと自由にしたい。制限の中で最初の寺尾聰さんの曲をどのように紹介しようかと思った時に、彼が手術で胃の8割を無くした時、その回復中に音楽制作を始めた。その時の曲が同じ『リフレクションズ』に収録されている「ルビーの指輪」だという話を入れました。こういうエピソードをさりげなく取り入れるのもDJの技なんですよ。
僕は子どもの頃から海外のラジオをいろいろチェックしていた。短波が聴けるようになって、いろいろな国の番組を聴きましたが最終的にはアメリカの番組にはかなわなくて、FENばかりを聴いていました。そうすると、向こうのスタイルというのがありますよね。日本では “サザンオールスターズの「いとしのエリー」です” と必ず曲紹介をしなくてはならない。
例えば、吉田拓郎の「結婚しようよ」を紹介するときも、曲名をそのまま告げるのではなく、男「君のことを待っているよ」女「いつまで待つの」男「じゃあこの曲を聴いて」っていう流れから「♪君の髪が肩まで伸びて~」と曲が始まるのがいい。それを作るのがDJの役目だと思っています。みんなが聴きたい吉田拓郎の曲なのに、そのまま曲名を告げるだけではダサいからね。
ビートルズの時代が来た時に “それではビートルズの「ヘルプ」です” から「♪Help~」って曲が始まるわけですよ。こんなダサいことないでしょ(笑)。だからこう言う場合は「ジョン、ポール&ジョージ、リンゴで行こうか!」とか、ビートルズというワードを避けるとか、そういうのは当たり前。これがエンタテインメントなんです。
僕は向こうのDJがそういうスタイルだということをわかって欲しかった。僕もそうあるべきだと思っていた。例えば「サンフランシスコで大変な事件が起きました。詳しくはCMの後で」とやるでしょ、あれもアメリカがやり始めたことで。
―― 克也氏のナレーションは単なる曲紹介に終始するのではなく、常に物語性を感じる。ナレーションにより楽曲本来の持ち味をより際立たせている。これは、これまで長きに渡り小林克也のスタイルとして貫いてきたことだと思う。今回は『~NIGHTTIME CITYPOP』ということで、これに加え、気を配った部分があるという。
克也:僕はNIGHTTIME担当。だから夜っぽいように “ささやき40%” のようなスタイルでやりました(笑)。夜のナレーションといえば『JET STREAM』の城達也さんを思い出す人もいるかもしれないけど、実は城さんのスタイルは僕と違う。彼はささやかない。あの人は声のトーンを落として2~3メートル先の人に話しかけるというスタイルです。彼は、収録時にはいつもドリンクを用意して、喉をウェットにしていました。
声に対するこだわりってありますよね。例えば、人間、本音が出るとき、低い声になる「実は僕は…」みたいにね。スネークマンショーの伊武雅刀はその声なんですよ。これをうまく使うことによって、物語性が生まれる。田村正和なんてすごいから。一層トーンを落として「僕はそんなこと知らないよ…」みたいにね。それを拾う映画の音声も大変だけど。彼も自分の良さがわかっていて、ああいう距離感でしゃべると自分の顔とスタイルが効果的に映るという計算があると思います。距離感はすごく大事なんです。

―― こういう部分も含めて、収録されている楽曲の素晴らしさが生きるということだろうか。今回収録されている楽曲に克也氏自身はどのような思いを抱いているのだろう。
克也:今回のアルバムに収録されている曲は、シティポップというジャンルの中にあるけれど、それぞれが違った個性を持つ都会の音楽として楽しむことが出来る。それぞれの個性がひしめき合う中でも、大貫妙子だけは、ジャンルにとらわれず相変わらずマイペースな印象があるね。
女性シンガーだと、今井美樹もオリジナリティが高い。昔彼女に「スマイリングボイス」と言ったことがあってね。そうしたら嫌われちゃって(笑)。というのは、英語で「スマイリングボイス」というのは笑っている声となりますよね。日本人だと玉置宏さんの司会の声かな。あれ、笑っている声ですよね。明るくて声が笑っている。今井美樹も同じようにスマイリングボイスなんですよね。だけど、ここに収録されている「Boogie-Woogie Lonesome High-Hee」では抑えている。そこがいい感じになって仕上がっていますね。
稲垣潤一はいいなと思っていました。寺尾聰も自分のスタイルを守っているから。あとブレッド&バターかな。彼らの「俺たちはこういうことしかやらないから」っていうスタイルがいいんです。だからスティーヴィーが曲を提供してくれた。スティーヴィー・ワンダーってそういう人ですよね。気に入った人間には提供する。「♪I just call~」っていう「心の愛」はブレバタがスティーヴィーからもらっているんですよね。
―― このような80年代に成熟していったシティポップの海外における再評価について克也氏はこう語る。
克也:若い人でも今回のシティポップを聴く人間がいることは知っている。それが広がるかどうかですね。それは何かのきっかけを待たなくてはならないと思う。例えば、東南アジアやヨーロッパでも日本のシティポップが盛り上がっているという情報がきっかけになる場合もある。アジアでシティポップが受けているというのは菊池桃子も話していました。アジアでも自分の楽曲をネットで観たり聴いたりしてくれる人がいて反響があると。かつての元気のあった日本だからああいうカルチャーが生まれたんだけど、それが、今経済的に成長している国々で聴かれている。そういう現状から広がりを見せる可能性もあります。
『DJ【小林克也】最新インタビュー ② 山下達郎「COME ALONG」と「ベストヒットUSA」』につづく
2023.05.03
80年代のラジオカルチャーは僕らに色々なことを教えてくれた。FM雑誌、エアチェック、そしてとびっきりのDJが道先案内人だった。当時、鈴木英人のイラストが表紙を飾っていたFM STAITIONとのコラボレートで、7月12日に2タイトルのシティポップオムニバスがリリースされる。そこには当時の珠玉のナンバーに加え、80年代の空気感を現代へと甦らせるDJの存在は欠くことができない。今回はリリースを記念してオムニバスCDのDJを務めた小林克也氏に当時のラジオ事情やDJとしての在り方、そして80年代に至るまでの音楽の成り立ちなど多岐にわたるテーマでお話を伺うことが出来た。
ウォークマンやビデオという新たなツールの登場。出来上がったミュージックビジネスの下地
―― FM雑誌が続々と創刊し、エアチェックのカルチャーが花開いた80年代、シティポップはどのように形成されて行ったのでしょう?
小林克也(以下克也):60年代、アメリカはビートルズに荒らされて、音楽シーンも一掃されたわけですよね。ミュージシャンたちもダンスミュージックだけではなく、芸術志向が高まってくる。ポップスにインテリ層が参加するようになって、社会的なメッセージも含め、広がりを見せてきます。当時音楽を志す人たちは、そういった高い望みを持つようになります。それまで最高とされていたマイルス・デイビスなんかがやっていたモダンジャズまで少なからぬ影響を受けています。子どもたちだけがターゲットではない社会的な問題を歌にするアーティストも出てきたりして、これも音楽が広がる大きなきっかけでしたね。
そんな中でレコード会社にすごく大きな変化が訪れます。70年代にキャロル・キングの『タペストリー』というアルバムが何百万枚と売れました。そうすると何十億という売り上げになりますよね。1枚のアルバムがそれだけのお金を動かすということがわかって、レコードは確率のいいバクチだと思われるようになる。レコード会社には映画会社の資本も入って、映画からヒット曲を生み出そうとする。つまり、この時期に現在に至るまでのミュージックビジネスの下地が完璧に出来上がったということです。
アメリカのこのような流れが日本にも浸透し、さらにウォークマンやビデオという新たなツールで音楽を楽しめるようになる。シティポップの流行にはそんな時代背景がありました。
井上鑑さんがプロデュースして大ヒットした寺尾聰の『リフレクションズ』は、画期的でした。録音の方法とか、ファンキーな要素を入れるとか、独特の感性がありました。このアルバムでやっているボーカルの多重録音なんかも井上鑑がスタートさせたもので、当時はみんなが真似しました。彼の功績はすごいんです。

「FM STATION 8090~GENIUS CLUB~ NIGHTTIME CITYPOP」に込められた小林克也の想い
―― 今回の『~NIGHTTIME CITYPOP』もこの『リフレクションズ』に収録された「出航 SASURAI」から幕を開ける。克也氏のナレーションは、まさしく、この『リフレクションズ』へのオマージュ、そして寺尾聰への賞賛だと思えてならない。ちなみに今回の台本もご自身が執筆している。これが小林克也のこだわりでもある。
克也:ナレーションの台本って制限がある。だけど、もっと自由にしたい。制限の中で最初の寺尾聰さんの曲をどのように紹介しようかと思った時に、彼が手術で胃の8割を無くした時、その回復中に音楽制作を始めた。その時の曲が同じ『リフレクションズ』に収録されている「ルビーの指輪」だという話を入れました。こういうエピソードをさりげなく取り入れるのもDJの技なんですよ。
僕は子どもの頃から海外のラジオをいろいろチェックしていた。短波が聴けるようになって、いろいろな国の番組を聴きましたが最終的にはアメリカの番組にはかなわなくて、FENばかりを聴いていました。そうすると、向こうのスタイルというのがありますよね。日本では “サザンオールスターズの「いとしのエリー」です” と必ず曲紹介をしなくてはならない。
例えば、吉田拓郎の「結婚しようよ」を紹介するときも、曲名をそのまま告げるのではなく、男「君のことを待っているよ」女「いつまで待つの」男「じゃあこの曲を聴いて」っていう流れから「♪君の髪が肩まで伸びて~」と曲が始まるのがいい。それを作るのがDJの役目だと思っています。みんなが聴きたい吉田拓郎の曲なのに、そのまま曲名を告げるだけではダサいからね。
ビートルズの時代が来た時に “それではビートルズの「ヘルプ」です” から「♪Help~」って曲が始まるわけですよ。こんなダサいことないでしょ(笑)。だからこう言う場合は「ジョン、ポール&ジョージ、リンゴで行こうか!」とか、ビートルズというワードを避けるとか、そういうのは当たり前。これがエンタテインメントなんです。
僕は向こうのDJがそういうスタイルだということをわかって欲しかった。僕もそうあるべきだと思っていた。例えば「サンフランシスコで大変な事件が起きました。詳しくはCMの後で」とやるでしょ、あれもアメリカがやり始めたことで。
僕はNIGHTTIME担当。だから夜っぽいように “ささやき40%”
―― 克也氏のナレーションは単なる曲紹介に終始するのではなく、常に物語性を感じる。ナレーションにより楽曲本来の持ち味をより際立たせている。これは、これまで長きに渡り小林克也のスタイルとして貫いてきたことだと思う。今回は『~NIGHTTIME CITYPOP』ということで、これに加え、気を配った部分があるという。
克也:僕はNIGHTTIME担当。だから夜っぽいように “ささやき40%” のようなスタイルでやりました(笑)。夜のナレーションといえば『JET STREAM』の城達也さんを思い出す人もいるかもしれないけど、実は城さんのスタイルは僕と違う。彼はささやかない。あの人は声のトーンを落として2~3メートル先の人に話しかけるというスタイルです。彼は、収録時にはいつもドリンクを用意して、喉をウェットにしていました。
声に対するこだわりってありますよね。例えば、人間、本音が出るとき、低い声になる「実は僕は…」みたいにね。スネークマンショーの伊武雅刀はその声なんですよ。これをうまく使うことによって、物語性が生まれる。田村正和なんてすごいから。一層トーンを落として「僕はそんなこと知らないよ…」みたいにね。それを拾う映画の音声も大変だけど。彼も自分の良さがわかっていて、ああいう距離感でしゃべると自分の顔とスタイルが効果的に映るという計算があると思います。距離感はすごく大事なんです。

それぞれが違った個性を持つ都会の音楽 “シティポップ”
―― こういう部分も含めて、収録されている楽曲の素晴らしさが生きるということだろうか。今回収録されている楽曲に克也氏自身はどのような思いを抱いているのだろう。
克也:今回のアルバムに収録されている曲は、シティポップというジャンルの中にあるけれど、それぞれが違った個性を持つ都会の音楽として楽しむことが出来る。それぞれの個性がひしめき合う中でも、大貫妙子だけは、ジャンルにとらわれず相変わらずマイペースな印象があるね。
女性シンガーだと、今井美樹もオリジナリティが高い。昔彼女に「スマイリングボイス」と言ったことがあってね。そうしたら嫌われちゃって(笑)。というのは、英語で「スマイリングボイス」というのは笑っている声となりますよね。日本人だと玉置宏さんの司会の声かな。あれ、笑っている声ですよね。明るくて声が笑っている。今井美樹も同じようにスマイリングボイスなんですよね。だけど、ここに収録されている「Boogie-Woogie Lonesome High-Hee」では抑えている。そこがいい感じになって仕上がっていますね。
稲垣潤一はいいなと思っていました。寺尾聰も自分のスタイルを守っているから。あとブレッド&バターかな。彼らの「俺たちはこういうことしかやらないから」っていうスタイルがいいんです。だからスティーヴィーが曲を提供してくれた。スティーヴィー・ワンダーってそういう人ですよね。気に入った人間には提供する。「♪I just call~」っていう「心の愛」はブレバタがスティーヴィーからもらっているんですよね。
―― このような80年代に成熟していったシティポップの海外における再評価について克也氏はこう語る。
克也:若い人でも今回のシティポップを聴く人間がいることは知っている。それが広がるかどうかですね。それは何かのきっかけを待たなくてはならないと思う。例えば、東南アジアやヨーロッパでも日本のシティポップが盛り上がっているという情報がきっかけになる場合もある。アジアでシティポップが受けているというのは菊池桃子も話していました。アジアでも自分の楽曲をネットで観たり聴いたりしてくれる人がいて反響があると。かつての元気のあった日本だからああいうカルチャーが生まれたんだけど、それが、今経済的に成長している国々で聴かれている。そういう現状から広がりを見せる可能性もあります。
『DJ【小林克也】最新インタビュー ② 山下達郎「COME ALONG」と「ベストヒットUSA」』につづく
2023.05.03
YouTube / avex
「FM STATION 8090」DAYTIME-NIGHTTIME
Information
あなた