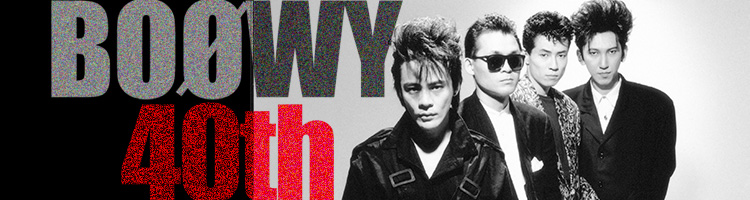この日何の日?
ザ・ストリート・スライダーズのアルバム「天使たち」がリリースされた日
この時あなたは
0歳
無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます
1986年のコラム
斉藤由貴の “胸キュンソング” ベストテン ♡ 際立つ言葉と歌唱の魔力♪
小泉今日子「木枯しに抱かれて」脱アイドル路線で女性ファンの支持を獲得!
80年代アイドルの2大片想いソングから読み解く、気温とヒットの不思議な関係
これぞ80年代のプレイリスト「BEAT EXPRESS」新しい音楽の楽しみ方!
孤高の存在、スライダーズのようなバンドはもう二度と現れないのだろうか
結成10年目のムーンライダーズが仕掛けた実験ポップ「30歳以上を信じるな」
もっとみる≫

photo:SonyMusic
ストリート・スライダーズ、村越弘明の生々しいカントリーブルースの“声”
ストリート・スライダーズというと、とにかくローリング・ストーンズと比較されることが多い。サウンド的にもストーンズやクリームといったブリティッシュロックを経由したブルース理解だな… というのはすぐ分かる。しかしそうした “白い” フィルターを通過しないで、ヴィヴィッドに伝わってくる “黒さ” もあるように思う。
その秘密はハリーこと村越弘明のボーカルにある。(常にではないが)特にシャウトするときなどハウリン・ウルフとかチャーリー・パットンといったカントリーブルース系歌手のダミ声に近づく奇跡的瞬間があり、アラン・ローマックスがフィールド・レコーディングしていた時代のアメリカ大陸の黒人音楽のプリミティヴさを感じる。これは日本人離れした生々しい声だと思う。
ブルース音楽に多大な貢献を果たした音楽批評家サミュエル・チャーターズが『ブルースの本』(晶文社)のなかで語っていたことだが、白人はブルースギターにばかり注目して、ブルースマンの声や歌詞にほとんど注目することがない。だからブルースが分からないのだと。
それは僕もその通りだと思っていて、ブルースギターは日々の生活の苦しみを歌う黒人の声に “彩り” を与える、あくまで副次的なものだろう。ブルースがテクニック偏重のデカダンスに陥って本質を見失わないためにも、やはりグリオ(語り部)としての土臭いワン&オンリーな “声” がなければならない。ハリーがそれだと思う。
佐久間正英プロデュース、転機となったアルバム「天使たち」
とはいえそうした土臭さだけがこのバンドの魅力ではない。五枚目のアルバム『天使たち』は頑なに続けていたセルフプロデュースの慣習を破って、元・四人囃子の佐久間正英をプロデューサーに迎えたバンドにとって転機となった一作(中森明菜『Stock』でミックスを担当したマイケル・ツィマリングも参加、『中森明菜のハードロックアルバム「Stock」前衛と官能の挟み撃ち!』参照)。そうしたこともあってか、サウンドはブルージーでありながら、ポップでニューウェーヴ的なきらびやかさも際立っている。
一曲目の「Boys Jump the Midnight」は代表曲で、冒頭のジャングルポップ風のギターはバーズなんかを想起させるクリーンさ。二曲目「Special Woman」はストーンズの「ホンキー・トンク・ウィメン」風のサビでワイルドさを維持しつつも、シンセキーボード音がチープに鳴り響いていてチャーミング。「Angel Duster」はフランジャーなのかリヴァーヴなのか、とにかくエフェクトを利かせまくったギターのサイケデリックな浮遊感が凄まじく、“エンジェルダスト” という(名前に反して悪魔的な)ドラッグの陶酔感を表現したものだと思う。とにかくヴァリエーション豊富だな… という印象を受けた。
ハリーと蘭丸、実は日本伝統のBLカルチャー?
蘭丸こと土屋公平がボーカルをとる「Lay down the City」も疾走感のある名曲だ。ハリーの野太い声が続いた後に、蘭丸のザラっとして少年っぽさの残る声が来ると対比が利いていておもしろい。
言うまでもなくカリスマ的なロックバンドはミック・ジャガーとキース・リチャーズ、デヴィッド・ボウイとミック・ロンソンなどなんでもいいが、フロントマンとギターのホモセクシュアルすれすれの、BL的妄想を掻き立てる “際どい” パフォーマンスがなければならない。スライダーズも一本のマイクでツインボーカルを取るとき、図らずもそうした伝統に属している。
しかしロックの範疇を越えて、これは日本文化の伝統でもある。女性ファンがつけたという “蘭丸” という綽名がすべてを物語っている。美童の蘭丸に対してワイルドなハリーが並ぶ姿は、森蘭丸と織田信長、あるいは牛若丸と弁慶の関係を想起させはしないか。
こうした美少年と侠客のような組み合わせは日本古来よく見られる革命を惹き起こすコンビであることを、異端江戸文学者・松田修が「幕末のアンドロギュノスたち」という文章で指摘している。スライダーズは黒人ブルースの世界のみならず、実は日本伝統のBLカルチャーにも属す革命的バンドだった。
あなたのためのオススメ記事
2021.10.14
Songlink
Information
あなた