この日何の日?
トーキング・ヘッズのアルバム「リメイン・イン・ライト」発売日
この時あなたは
0歳
無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます
1980年のコラム
貸レコード屋「黎紅堂」で出逢った心の愛人、門あさ美
女子大生ブームの扉を開けた宮崎美子、いまのキミはピカピカに光って!
警視-K、勝新太郎はシュガーベイブの夢を見る
2023年を感じながら聴く【80年代ロック名盤ベスト10】懐かしむより超えていけ!
まさかの出入禁止!ユーミンに怒られた「ワンダフルcha-cha」制作顛末
クール&ザ・ギャングとEW&F、ゆずとコブクロって全然違うでしょ!?
もっとみる≫

リ・リ・リリッスン・エイティーズ〜80年代を聴き返す〜 Vol.46
Talking Heads / Remain in Light
ポップミュージックはまず「ポップ」であらねばならないが、同時に「ヒネリ」がなければならない、というのが私の “基本姿勢” です。15の頃、ビートルズを聴いているうちに、言葉にできない幸福感に包まれたのが、私の初 “感動” 体験です。後年その原因は何かと探って、得た答えが「ポップ」と「ヒネリ」でした。ポップで楽しい、でもどこか一筋縄ではいかない、そんな感じ。
以来、それが音楽を聴く際のモノサシとなっています。もちろん、圧倒的に歌声が素晴らしいなど、ヒネリなどなくても聴き惚れてしまうような音楽もありますが、それは例外的。
ただモノサシと言っても、1mm単位の細かな目盛りがあるわけではなく、かなりザックリとしたものです。そもそも「ポップ」も「ヒネリ」自体も、そうであるかないかの境界線は曖昧だし、人それぞれに感じ方も違うでしょう。私は自分では、「ポップ多めのヒネリ少々」が好きなつもりなんですが、なぜか周りの人はよく私をマニアックだと評します。つまり、ヒネリ多めが好きだと思われているのです。人にどう思われようがかまいませんが(ホントは気になるけどね…)、世の中、私よりヒネリ好きな人は五万といるのに、私ごときでマニアックとは逆に恐れ多いというか、なぜなんだろう?
その疑問への私なりの答えは、「ポップ度高=売上大=有名、ヒネリ度高=評価高=有名」という “方程式” です。これはなんとなく分かりますよね。で、これで言えることは、「ポップ度高」も「ヒネリ度高」も同様に有名なんだけど、群がっている人数は「ポップ度高」のほうが圧倒的に多いってことです。だって「売上大」ってそういうことですから。だから、ちょっとヒネリ好きなら、目立ってしまい、「ヒネリ度高」側に入れられてしまうのでしょう。
なんか冒頭からウダウダと申し訳ないですが、何を言いたいかといいますと、私の好きな加減よりヒネリ度の高い音楽が、ずいぶん高評価を受けているのは、どうなのか、ってことなんです。いや、事実に文句を言うつもりも、自分が正しいと主張するつもりもまったくなくて、ホントにみんなそう思ってるの?ちょっと難解なものを褒めといたほうがカッコいいなんて思ってるんじゃないの?といった、“下衆の勘ぐり” なんですが。
ということで、“トーキング・ヘッズ” の『リメイン・イン・ライト(Remain in Light)』。1980年10月に発売された、4作目のアルバムです。アフリカ的なファンク・サウンドを大胆に取り入れた意欲作として、「New York Times」や「Melody Maker」や「NME」はじめ、米英の多くのメディアで「1980年のベストアルバムのひとつ」という高い評価を受けました。この「リ・リ・リリッスン・エイティーズ」が今回46回目にしてようやく、本アルバムを取り上げていることでお分かりのように、1980年に発売された中で、私が重要と考えるアルバムだけでも45作品以上あるのです(重要度順に選んでいるわけではありませんが…)。
本作はそれなりに売れてはいますが、全米19位、全英21位で、大ヒットとは言えないし、バンドの他のアルバムに比べても、突出しているわけではありません。だけど評価は突出しています。前述の他にも、たとえば定番の「ローリングストーン誌が選ぶ歴代最高のアルバム500選」。300人以上のアーティスト、プロデューサー、評論家、音楽業界関係者から、それぞれが考えるトップ50アルバムのリストを出してもらい、集計したものですが、その2020年版で、『リメイン・イン・ライト』は39位という上位に選出されています。バンドのアルバムで他にランクインしているものはセカンドアルバムの『モア・ソングス(More Songs About Buildings and Food)』だけで、それは364位です。

だけど私には、本作が彼らの他の作品よりも、突出はおろか、勝っているとも思いません。もとよりポップとヒネリを兼ね備えた音楽性なので、大好きなバンドのひとつなのですが、このアルバムはバランス的にヒネリに偏りすぎています。曲としてよいと思えるのは、つまりポップ度も確保しているのは、(LPだと)B面2曲目の「ハウシズ・イン・モーション(Houses in Motion)」だけ。「ワンス・イン・ア・ライフタイム(Once in a Lifetime)」は代表曲のひとつとされていますが、ポップさに“切れ”がなく、凡作だと思います。このアルバムの中ではいちばん分かりやすいから目立っているのでしょう。
本作に取り掛かる頃、それまでほぼすべての詞曲をつくっていたデヴィッド・バーン(David Byrne)はスランプだったみたいですね。バハマにあるコンパス・ポイント・スタジオでレコーディングを開始しましたが、曲がなくて、メンバー4人でひたすらフリーセッションに明け暮れます。セカンド & サードとプロデュースを務めたブライアン・イーノは、今回は断ろうと思っていたようですが、遅れてスタジオに合流し、セッションテープを聴くと、俄然やる気になりました。ふつうの人なら曲がひとつもできていない状況に困惑するだけでしょうが、あの人は奇才だから、ふつうのやり方じゃないほうが燃えるみたいです。
最終的にどんな曲にするのか、あえて決めないまま、いろんなリズムパターンの演奏を録音し、そのテープをループにして繰り返したり、パターンの組み合わせをあれこれ変えたり…… というような作業で曲がつくられていったようです。当時は「サンプラー」などありませんでしたが、イーノは後に「我々は人間サンプラーだった」と語っています。
たしかに未知の領域に挑戦することは立派だと思います。それがなければ、新しい驚きも喜びも生まれてこない。ただそれだけなら「実験」で、実験は成果を伴って初めて評価に値します。『リメイン・イン・ライト』はたしかにポップスの常識を打ち破ったという点で、画期的かもしれませんが、コードの概念を捨て、新しいグルーヴを追求して、楽曲の構造に大きな変化をもたらすというイーノの大胆な「実験」に対して、バーンはそれに見合うだけのポップセンスを発揮できませんでした。もしバーンがスランプ状態でなければ、本当にすごいアルバムが誕生していたかもしれません。
デヴィッド・バーンは本来、豊かなポップセンスの持ち主だと思っています。時代はグッと下って、映画『アメリカン・ユートピア(American Utopia)』(2020)------バーンのブロードウェイ公演をスパイク・リー(Spike Lee)監督が映画化したもの------を観たのですが、神経質な哲学者然としたイメージの人だったバーンが、エンタテイナーとしても実にプロフェッショナルで、アラコキ(ほぼ古希)とは思えない魅力的なオーラを放っていることに驚きました。
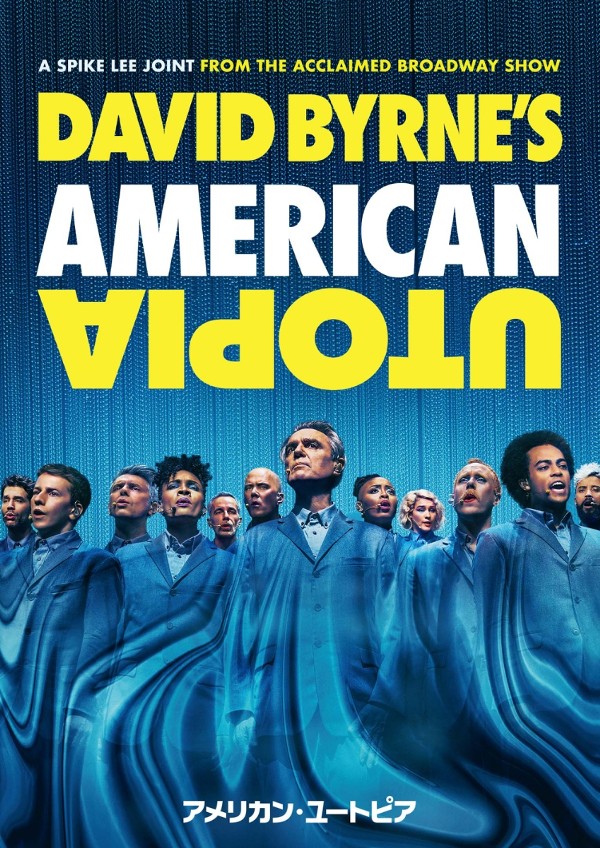
40年前の彼も、実験のまま終わったわけではありませんでした。『リメイン・イン・ライト』でイーノからは卒業し、次作『スピーキング・イン・タングズ(Speaking in Tongues)』(1983年)では、ポップ&ヒネリのバランスが適正な、「バーニング・ダウン・ザ・ハウス(Burning Down the House)」という代表曲(これこそ!)に辿り着くのです。
2023.10.11
Talking Heads / Remain in Light
「ポップ」と「ヒネリ」
ポップミュージックはまず「ポップ」であらねばならないが、同時に「ヒネリ」がなければならない、というのが私の “基本姿勢” です。15の頃、ビートルズを聴いているうちに、言葉にできない幸福感に包まれたのが、私の初 “感動” 体験です。後年その原因は何かと探って、得た答えが「ポップ」と「ヒネリ」でした。ポップで楽しい、でもどこか一筋縄ではいかない、そんな感じ。
以来、それが音楽を聴く際のモノサシとなっています。もちろん、圧倒的に歌声が素晴らしいなど、ヒネリなどなくても聴き惚れてしまうような音楽もありますが、それは例外的。
ただモノサシと言っても、1mm単位の細かな目盛りがあるわけではなく、かなりザックリとしたものです。そもそも「ポップ」も「ヒネリ」自体も、そうであるかないかの境界線は曖昧だし、人それぞれに感じ方も違うでしょう。私は自分では、「ポップ多めのヒネリ少々」が好きなつもりなんですが、なぜか周りの人はよく私をマニアックだと評します。つまり、ヒネリ多めが好きだと思われているのです。人にどう思われようがかまいませんが(ホントは気になるけどね…)、世の中、私よりヒネリ好きな人は五万といるのに、私ごときでマニアックとは逆に恐れ多いというか、なぜなんだろう?
その疑問への私なりの答えは、「ポップ度高=売上大=有名、ヒネリ度高=評価高=有名」という “方程式” です。これはなんとなく分かりますよね。で、これで言えることは、「ポップ度高」も「ヒネリ度高」も同様に有名なんだけど、群がっている人数は「ポップ度高」のほうが圧倒的に多いってことです。だって「売上大」ってそういうことですから。だから、ちょっとヒネリ好きなら、目立ってしまい、「ヒネリ度高」側に入れられてしまうのでしょう。
突出して高評価な「リメイン・イン・ライト」
なんか冒頭からウダウダと申し訳ないですが、何を言いたいかといいますと、私の好きな加減よりヒネリ度の高い音楽が、ずいぶん高評価を受けているのは、どうなのか、ってことなんです。いや、事実に文句を言うつもりも、自分が正しいと主張するつもりもまったくなくて、ホントにみんなそう思ってるの?ちょっと難解なものを褒めといたほうがカッコいいなんて思ってるんじゃないの?といった、“下衆の勘ぐり” なんですが。
ということで、“トーキング・ヘッズ” の『リメイン・イン・ライト(Remain in Light)』。1980年10月に発売された、4作目のアルバムです。アフリカ的なファンク・サウンドを大胆に取り入れた意欲作として、「New York Times」や「Melody Maker」や「NME」はじめ、米英の多くのメディアで「1980年のベストアルバムのひとつ」という高い評価を受けました。この「リ・リ・リリッスン・エイティーズ」が今回46回目にしてようやく、本アルバムを取り上げていることでお分かりのように、1980年に発売された中で、私が重要と考えるアルバムだけでも45作品以上あるのです(重要度順に選んでいるわけではありませんが…)。
本作はそれなりに売れてはいますが、全米19位、全英21位で、大ヒットとは言えないし、バンドの他のアルバムに比べても、突出しているわけではありません。だけど評価は突出しています。前述の他にも、たとえば定番の「ローリングストーン誌が選ぶ歴代最高のアルバム500選」。300人以上のアーティスト、プロデューサー、評論家、音楽業界関係者から、それぞれが考えるトップ50アルバムのリストを出してもらい、集計したものですが、その2020年版で、『リメイン・イン・ライト』は39位という上位に選出されています。バンドのアルバムで他にランクインしているものはセカンドアルバムの『モア・ソングス(More Songs About Buildings and Food)』だけで、それは364位です。

画期的だけど、それだけ!?
だけど私には、本作が彼らの他の作品よりも、突出はおろか、勝っているとも思いません。もとよりポップとヒネリを兼ね備えた音楽性なので、大好きなバンドのひとつなのですが、このアルバムはバランス的にヒネリに偏りすぎています。曲としてよいと思えるのは、つまりポップ度も確保しているのは、(LPだと)B面2曲目の「ハウシズ・イン・モーション(Houses in Motion)」だけ。「ワンス・イン・ア・ライフタイム(Once in a Lifetime)」は代表曲のひとつとされていますが、ポップさに“切れ”がなく、凡作だと思います。このアルバムの中ではいちばん分かりやすいから目立っているのでしょう。
本作に取り掛かる頃、それまでほぼすべての詞曲をつくっていたデヴィッド・バーン(David Byrne)はスランプだったみたいですね。バハマにあるコンパス・ポイント・スタジオでレコーディングを開始しましたが、曲がなくて、メンバー4人でひたすらフリーセッションに明け暮れます。セカンド & サードとプロデュースを務めたブライアン・イーノは、今回は断ろうと思っていたようですが、遅れてスタジオに合流し、セッションテープを聴くと、俄然やる気になりました。ふつうの人なら曲がひとつもできていない状況に困惑するだけでしょうが、あの人は奇才だから、ふつうのやり方じゃないほうが燃えるみたいです。
最終的にどんな曲にするのか、あえて決めないまま、いろんなリズムパターンの演奏を録音し、そのテープをループにして繰り返したり、パターンの組み合わせをあれこれ変えたり…… というような作業で曲がつくられていったようです。当時は「サンプラー」などありませんでしたが、イーノは後に「我々は人間サンプラーだった」と語っています。
たしかに未知の領域に挑戦することは立派だと思います。それがなければ、新しい驚きも喜びも生まれてこない。ただそれだけなら「実験」で、実験は成果を伴って初めて評価に値します。『リメイン・イン・ライト』はたしかにポップスの常識を打ち破ったという点で、画期的かもしれませんが、コードの概念を捨て、新しいグルーヴを追求して、楽曲の構造に大きな変化をもたらすというイーノの大胆な「実験」に対して、バーンはそれに見合うだけのポップセンスを発揮できませんでした。もしバーンがスランプ状態でなければ、本当にすごいアルバムが誕生していたかもしれません。
デヴィッド・バーンは本来、豊かなポップセンスの持ち主だと思っています。時代はグッと下って、映画『アメリカン・ユートピア(American Utopia)』(2020)------バーンのブロードウェイ公演をスパイク・リー(Spike Lee)監督が映画化したもの------を観たのですが、神経質な哲学者然としたイメージの人だったバーンが、エンタテイナーとしても実にプロフェッショナルで、アラコキ(ほぼ古希)とは思えない魅力的なオーラを放っていることに驚きました。
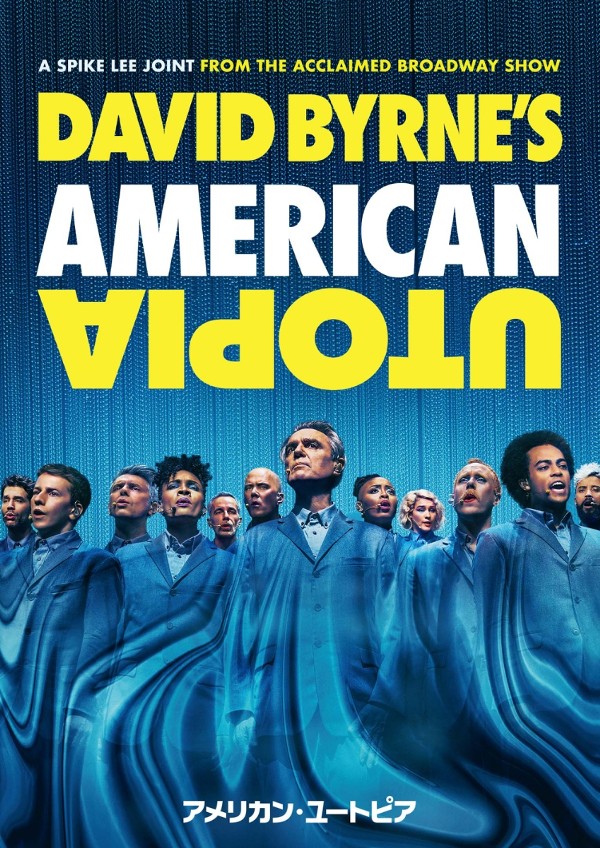
40年前の彼も、実験のまま終わったわけではありませんでした。『リメイン・イン・ライト』でイーノからは卒業し、次作『スピーキング・イン・タングズ(Speaking in Tongues)』(1983年)では、ポップ&ヒネリのバランスが適正な、「バーニング・ダウン・ザ・ハウス(Burning Down the House)」という代表曲(これこそ!)に辿り着くのです。
アナタにおすすめのコラム
2023.10.11
Songlink
Information
あなた
























