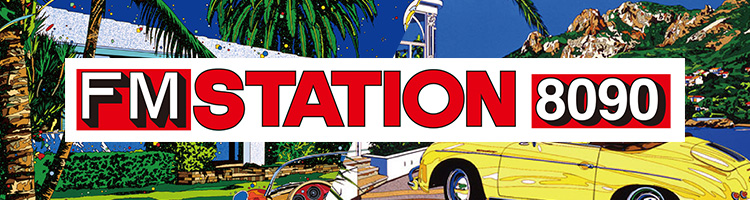この日何の日?
FM情報誌「FM STATION」創刊日
この時あなたは
0歳
無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます
1981年のコラム
第1期アリス最後のアルバム「ALICE IX 謀反」グラサン姿の3人もただごとではない!
機動戦士ガンダムⅡ ー 明日という未来に希望を持たせてくれた「哀 戦士」
井上大輔が80年代に果たした功績、貫かれたロックンロール小僧のスピリット!
FM STATION の時代《カセットテープ・ミュージック》エアチェックはFM雑誌が生命線!
全米ヒットチャートに夢中!若者のバイブル “FM情報誌” とエアチェックの時代
80年代のスタートは1981年? 日本人にどんどん浸透していったアメリカの風
もっとみる≫

ウォークマンⅡの発売と「ベストヒットUSA」のスタート、そしてFM情報誌戦国時代へ
音楽好きにとって、1981年は奇跡の年だった。
その年、2月に初代を上回る大ヒットとなる「ウォークマンⅡ」が発売され、3月にはシティポップの名盤、大滝詠一の『A LONG VACATION』がリリース。4月にはNHK-FMの『サウンドストリート』に佐野元春が登場し、同月、テレビ朝日は小林克也を司会に『ベストヒットUSA』をスタートさせた。
6月には寺尾聡の「ルビーの指環」が『ザ・ベストテン』で12週連続1位となり、7月には業界4誌目となるFM情報誌『FM STATION』(ダイヤモンド社)が創刊され、同業界は戦国時代に突入。8月にはアメリカで24時間、ポピュラー音楽のビデオクリップを流し続ける音楽専門チャンネル『MTV』が開局し、9月には『ザ・ベストテン』が番組史上最高視聴率41.9%を記録した――。
そう、そんな音楽絡みの大イベントが頻発した奇跡の年、1981年。これらの中で、特に注目したいトピックスが、「ウォークマンⅡ」の発売と「ベストヒットUSA」のスタート、そしてFM情報誌戦国時代である。

80年代の音楽ライフスタイル、エアチェック
これに、1979年発売のサンヨーのおしゃれなテレコ「U4」を合わせると、ある行動が見えてくる。
――“エアチェック”だ。若い世代にはピンとこないワードかもしれない。ラジオのFM放送のオンエアから楽曲だけをピックアップし、録音するスタイルを、かつて僕らはそう呼んだ。お目当ての流行りの音楽を、FM情報誌で放送日時を予習し、ラジカセでカセットに録音して、ウォークマンⅡに入れて持ち歩く―― それが僕らの80年代の音楽ライフスタイルだった。
FM情報誌はご丁寧に1曲あたりの尺も記し、番組は曲にDJの声がかぶらないように配慮した。すべてはリスナーのエアチェックのためだった。
いや、厳密には、それは“80年代前半” の音楽ライフスタイルだったとも――。一口に80年代と言っても、前半と後半では、音楽を取り巻く環境も大きく異なる。思えば、80年代前半は、日本人が最も洋楽に接近した時代だった。思いつくままに、当時流行った洋楽を挙げると――
―― ボーイズ・タウン・ギャング「君の瞳に恋してる」、ヴァンゲリス「炎のランナー」、シカゴ「素直になれなくて」、ジョー・コッカー&ジェニファー・ウォーンズ「愛と青春の旅だち」、マイケル・ジャクソン「スリラー」「今夜はビート・イット」、TOTO「ロザーナ」「アフリカ」、サバイバー「アイ・オブ・ザ・タイガー」――
―― カルチャークラブ「カーマは気まぐれ」、ビリー・ジョエル「アップ・タウン・ガール」、アイリーン・キャラ「フラッシュダンス」、ポリス「見つめていたい」、デビット・ボウイ「レッツ・ダンス」――
―― a-ha「テイク・オン・ミー」、ヴァン・ヘイレン「ジャンプ」、シンディ・ローパー「ハイ・スクールはダンステリア(※後に「ガールズ・ジャスト・ワナ・ハヴ・ファン」に改題)」、リマール「ネバーエンディング・ストーリー」、レイ・パーカー・ジュニア「ゴーストバスターズ」、ケニー・ロギンス「フットルース」――
―― プリンス「ビートに抱かれて」、スティービー・ワンダー「心の愛」「パートタイム・ラヴァー」、デュラン・デュラン「ザ・リフレックス」、マドンナ「ライク・ア・ヴァージン」、フレディ・マーキュリー「ボーン・トゥ・ラヴ・ユー」、ワム!「ケアレス・ウィスパー」「ラスト・クリスマス」、ブルース・スプリングスティーン「ボーン・イン・ザ・U.S.A.――
―― ライオネル・リッチー「セイ・ユー、セイ・ミー」、ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース「パワー・オブ・ラヴ」―― ふぅ、疲れた。

いや、これらはほんの一例。正直、洋楽にあまり詳しくないという人も、これらのタイトルを見ただけで、勝手に脳内で音楽が再生されるだろう。あるいは、タイトルを知らなくても、これらのイントロやサビが流れたら、誰しも、あぁ!と耳が反応する曲ばかりだ。
思想より感性が優先された時代の洋楽
そう、これが “80年代前半” の洋楽の特徴である。どれもメロディに優れ(ポップ)、思想がなく(ノン・ポリティカル)、大衆的だった(エンタテインメント)。つまり、洋楽ファンでもなんでもない、ごく普通の日本の若者たちが、まるで歌謡曲やアイドルソングに接するように、気軽に洋楽に接した時代―― それが、80年代前半だった。
僕は昨年、『黄金の6年間 1978-1983〜素晴らしきエンタメ青春時代』(日経BP)という本を出した。Re:minderで連載していたコラムをまとめた本である。
―― それは、1978年から83年の6年間に注目し、その時代、音楽に限らず、テレビや映画、小説など、あらゆるエンタメの分野で垣根を超えたクロスオーバーが進み、今に繋がる新人たち(例えば、松田聖子、サザンオールスターズ、ビートたけし、村上春樹ら)が多数輩出された―― と説いたもの。
背景に、1975年のベトナム戦争終結を起点とするエンタメ市場の “自由化” があり、思想より感性が優先された時代だったと結論づけた。

「サタデー・ナイト・フィーバー」を起点とする新しい音楽時代の幕開け
そう、先の80年代前半の洋楽が、まさに、この「黄金の6年間」と重なる。むしろ、ベトナム戦争終結を起点に、若者カルチャーがより大きく変貌したのは、本場アメリカのほうである。
ベトナムから帰国した元兵士の若者たちにより、西海岸のアウトドア文化が花開き、バッドエンドな「アメリカン・ニューシネマ」に替わって、ルーカスやスピルバーグら若手旗手たちの手でハッピーエンドのハリウッド映画が復活した。
時に、合衆国大統領も1980年に元俳優のレーガンが就任。減税と規制緩和を柱としたレーガノミクスでアメリカ経済は復活し、人々は黄金の80年代を謳歌する。
そんな時代に、アメリカの音楽も大きく変わる。まず、ベトナム戦争を背景にラブ&ピースを掲げたプロテストソングは、70年代後半、皆で歌い踊るディスコミュージックへと変貌する。映画『サタデー・ナイト・フィーバー』を起点とする新しい音楽時代の幕開けだった。
目で聴く音楽へ。極めてエンタテインメント性の高い作品だった「スリラー」
次に1980年、ジョン・レノンが射殺され、いよいよ思想の時代の70年代が終わりを告げる。それと入れ替わるように翌81年、ビデオクリップで音楽を紹介する『MTV』がスタートし、音楽は映像と一体化してセールスされるように。
その象徴が、83年にシングルカットされたマイケル・ジャクソンの「スリラー」だった。ジョン・ランディスが手掛けたミュージックビデオは、14分もの短編映画風であり、極めてエンタテインメント性の高い作品だった。
それ以降、音楽と映像は切っても切れない関係となる。俗に、人間が五感から受ける情報の9割は視覚情報であり、耳で聴く音楽から、ミュージックビデオなど目で聴く音楽へ――。そこから、シンディ・ローパーやマドンナら極めてフォトジェニックなアーティストが脚光を浴びるようになり、あるいは、まんま映画の主題歌が大ヒットする時代へ――。
ちなみに、1967年生まれの僕自身、“音楽・奇跡の年” の1981年が中学2年で、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の主題歌「パワー・オブ・ラヴ」が大ヒットした1985年が高校3年と、人生において最も多感なミドルティーンがすっぽり80年代前半と重なる。そんな僕らの世代の音楽ライフは当時、邦楽は『ザ・ベストテン』、洋楽は『ベストヒットUSA』を毎週欠かさず見て、FM情報誌でお目当ての楽曲の放送日を予習して、エアチェックするのが日課だった。
表紙は鈴木英人のイラストだった「FM STATION」
正直、武骨な初代ウォークマンは敷居が高かった僕らも、スタイリッシュになり、サイズもひと回り小さくなったウォークマンⅡは、お年玉をはたいて、迷わず買った。そう、人の購買動機に最も有効な手立てはデザイン―― 僕があの時、学んだ人生の哲学である。
そして、エアチェック用に重宝したのがFM情報誌で、僕らの間では『FMレコパル』(小学館)派と『FM STATION』(ダイヤモンド社)派が半々だったと記憶する。あとの老舗の2誌『FM Fan』(共同通信社)と『週刊FM』(音楽之友社)は、もう少し上の世代を狙っていたと思う。
レコパルはコラム記事と連載が面白く、一方のSTATIONは、なんと言っても鈴木英人(すずき・えいじん)サンが手掛ける表紙のイラストと、付録のカセットケースのレーベルが魅力的だった。僕自身は、両誌をパラパラと見比べて、その時々の気分でどちらかを買っていたと思う。
エアチェックする楽曲は洋楽6:邦楽4で、洋楽が多かった。それは、マイ編集したカセットケースに、洋楽のタイトルが並ぶほうがカッコよく、時に友人らと貸し借りが行われたからである。
邦楽も、もっぱら入れるのは、佐野元春や大滝詠一、ユーミン、南佳孝、山下達郎らポップス勢(当時はシティポップと呼んでなかった気がする)ばかり。松田聖子や中森明菜らアイドルソングを納めたテープは、部屋の奥深くに隠された。
そうそう、当時はカセットテープにも流派があった。SONY派、TDK派、maxell派―― 生まれついてのソニーっ子だった僕は、もっぱらSONYのAHF46を愛用した。46とは46分録音できるという意味で、それはLPの収録時間であり、多くの人はこの「46」を購入した。よく考えたら、自分でテープを編集するので、LPのサイズにこだわる意味はないが、なぜか46が音質的に最も優れていると思っていた。

音楽の世界へナビゲート、大人の世界を覗き見るFMラジオの世界
当時、僕らの世代によく聴かれていたFM番組は、22時から、先にも書いたNHK-FMの『サウンドストリート』、続いて23時から『クロスオーバー・イレブン』―― これは、俳優の津嘉山正種サンのナビゲートがカッコよく、且つ選曲もイカしていた。
それが終わると、JFN系列にダイヤルを移し、24時から城達也サンの『ジェットストリーム』―― その流れが、平日夜の定番だった。ミドルティーンエイジャーにとって、ひとり部屋で聴くFMラジオは、大人の世界を覗き見るようだった。
思えば、FMラジオほど、昔と今で、聴き方が大きく変わったメディアもないだろう。かつてのそれは、音楽の世界へナビゲートしてくれる大人のメディア。時に、言葉よりも音楽が意味を持った。僕らは2週間前にタイムテーブルを予習し、エアチェックしたい番組を丸で囲った。まるで儀式のようなその時間がとても楽しかったのを覚えている。
ところが80年代後半、レンタルレコードが普及し、さらに時を経ずにCD化の波が押し寄せる。80年代末、僕らは聴きたい楽曲をレンタルCDからカセットテープへダビングするようになった。もはやエアチェックの習慣は廃れ、自分でテープを編集することもなくなった。FM情報誌はおろか、FM番組を聴く機会もめっきり減った。
ある時、独立系のFM放送を聴くと、「モア・ミュージック、レス・トーク」とばかりに、ひたすら音楽ばかりを流していた。悪くはなかったが、何か物足りないと感じた。また、しばらくして、久しぶりにJFN系列の番組を聴くと、今度はAMラジオのように生放送のトーク番組に様変わりしていた。僕はそっと、ラジオの主電源をオフにした。
気がつけば―― 僕自身、洋楽と接する機会は激減し、周囲はJ-POPばかりが氾濫していた。久しぶりに書店で見かけたFM STATIONは、表紙が鈴木英人サンから別のイラストレーターに変わっていた。
時に90年代―― 夏が、終わろうとしていた。
アナタにおすすめのコラム
2023.04.26
Songlink
Information
あなた