この日何の日?
UP-BEATのアルバム「BEAT-UP ~UP-BEAT Complete Singles~」がリリースされた日
この時あなたは
0歳
無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます
2022年のコラム
早見優インタビュー ③ 40周年企画始動、様々なアーカイブに加えていよいよ新曲も!
バブルの真っ只中に現われた香港映画「男たちの挽歌」トレンディなんてブッ飛ばせ!
デビュー50周年!チューリップが一瞬で引き戻してくれた “青春の時間”
甲斐よしひろ「FLASH BACK」数多のカバー曲とソロ活動35周年アルバムの関係
広石武彦に訊くUP-BEAT ② ホッピー神山、是永巧一、佐久間正英という3人のプロデューサー
ソロデビュー40周年を迎えた増田惠子、ピンク・レディーもデビュー45周年!
もっとみる≫

第3回
僕の歌詞は基本 “負け犬” 負けてるヤツが、それでも…って続いていった。それがUP-BEAT
― 広石さんは映画、松本隆さんの『微熱少年』にも出演されていますよね。
広石:松本隆さんには「この映画に出演する役者は本当のミュージシャンでなければならない」というこだわりがあって、当時数多く発行されていた邦楽の音楽雑誌をチェックしたなかで僕の目が良いって、気に入って下さったらしくて。それでお会いして話したんですが、キャスティング自体は当時の事務所が主導して決めたことで、僕は出演がすでに決まっていたことを知りませんでした。松本さんが帰ってからの助監督さんとの打ち合わせで「あ、俺この映画に出るんだ」と気付いたくらいです。だけど、受けたからには一生懸命やりましたよ。それにあの映画に出演したおかげで松田聖子さんに楽曲提供することもできましたし。「チャンスは2度ないのよ」という曲です。
― 今のお話を聞いていて、売れることは確かに大事で、そのために事務所も試行錯誤しつつ…。
広石:『微熱少年』はファーストの頃だから、いろんなことがありましたよ。誰も焦点が定まってない時期でした。そこを是永さんがまとめてくれたのがファーストアルバムです。だけど、僕らが演奏しているわけじゃないから『IMAGE』というタイトルにしました。これはUP-BEATのイメージだからと。そこから、「俺たち進歩していこうぜ!」ってガツンと。
― その時、メンバー5人が一枚岩で向かっていく感じでしたか?
広石:だんだんそうなっていく感じでした。だけど、UP-BEATは最後まで完全な一枚岩ではなかったです。僕が強引に引っ張ってました。
― 僕も広石さんのイニシアチブをなんとなく分かってはいました。それでもメンバーと見ているところが違うと、バンド継続が難しい部分があると思いますが。
広石:メンバー全員が同じ方向を見ているという、僕の思い込みが強かったんだと思います。
― 広石さんの中で、こういうバンドを目指そう、こういう風になるためには、ここと、ここが必要だよっていうところが実は違っていたと。それに気づいたのはいつぐらいですか?
広石:僕がインタビューでよく話す例えですが、「バンドっていうのは虫メガネみたいなものだよ」と。虫メガネというのは、光を一点に集中して集めると、なんだって焦がして、最後は突き抜けていっちゃうじゃないですか。これがバンドなんです。でも見ている向きが違う人たちに話しても、その人の心に響くかどうかは分からないですよね。だけど、僕はメンバーに一方的にそういうことを言ってました。
― 広石さんには意地もあったと思うし、どんどん良いアルバムを出していきますよね。音楽性が深化していく中にもバンドとして変わらないスタンスもある。広石さんの存在感もずっと変わらなかったと思います。
広石:セカンドのレコーディングが終わって、僕はかなり無理をしていたんでしょうね。全然曲が書けなくなりました。そのタイミングでディレクターが変わったんですがその新しいディレクターの方が僕を休ませてくれたんです。「レコーディングが止まってもいいから、何か月か休んでいいよ」と。あれは本当にありがたかったです。
― UP-BEATがデビューしてから長い期間、それだけ真正面から向き合っていれば心労も相当だったと思います。
広石:心労すごかったですよ。毎日あんまり面白くないですよね(笑)。
― ライブとかはどうでした。熱狂するファンも多かったと思いますが。
広石:僕自身完成していなかったし、自分の歌唱にも自信を持てていなかったから、疑心暗鬼になっていましたね。一生懸命やっているんだけど、良かったのかどうなのか分からない。ずっともがいてる感じでした。でも、何故今みたいに歌えなかったのか?と考えてもわからないんです。
― 今が一番いいということですね。
広石:多分そうです。
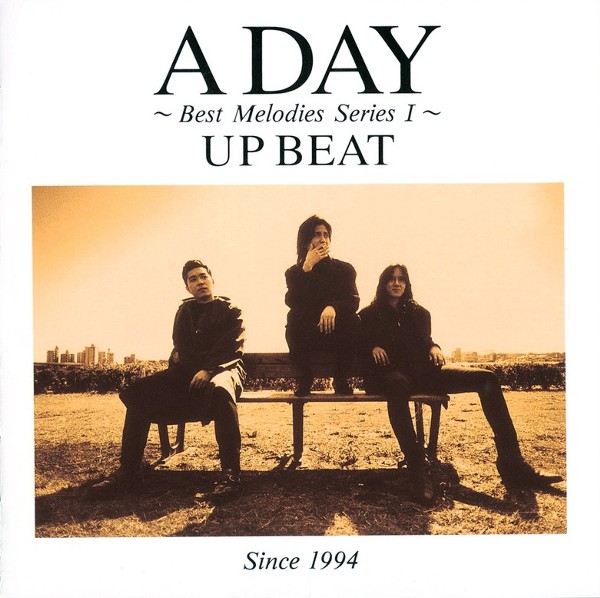
― 今回は、シングルのコンプリートがリマスターでリリースされますが、リリース順にお聴きになってどうですか?
広石:僕自身の後からの目線だと全部惜しいんですよ。あと少しが足りない…。歌にしても何にしても。過去に一回だけ、「Sister Tomorrow –Still I Miss You-」というシングル曲をやり直したことがあるんですよ。(註:ミニアルバム『A DAY』でリメイク収録した)
これは僕の中で完璧な出来なんですね。何故それが、最初に出来なかったのかと考えると、疲れてたんです。いざ歌う最後の段の時にそれまでの作業によって、ヘトヘトになっているんです。レコーディングはそんな感じで疲れている分、本人的には突き抜けていない印象を持ってしまうというか…。
― 意外ですね。これだけ煌びやかな世界を作り上げているのに、その中でも苦悩があったんですね。しかし今回のマスタリングで変わって聴こえてくる部分もありますよね。
広石:魔法ですね! マスタリングエンジニアの方は素晴らしいです!
― UP-BEATのようなバンドはシングルコンプリートで出す意義がすごく大きいと思います。バンドの変化が見えるじゃないですか。
広石:シングルだけは、シングルっぽく作らなきゃと思っていました。だからUP-BEATってアルバムを聴くと評価が変わると思います。
― シングルは幅広い層に届けるためにということですね。
広石:そうです。佐久間さんの対応もセカンド以降は真逆になっていくんです。自分たちはライブもやって、ツアーもこなして普通に上手くなっていました。すると、セカンドであれだけ厳しかった佐久間さんが「間違っていることは僕が正すからそれ以外は好きにやりなさい」と。それが『HERMIT COMPLEX』でした。

― ここでUP-BEATらしさを全面に出せたと。
広石:ギターの岩永(凡)らしさを初めて出せたのが『HERMIT COMPLEX』だと思います。骨太いバンドっぽくしたかったんです。そう思っていた時期に佐久間さんは好きにやらせてくれて。
― そこでバンドのグルーヴをしっかり出せて、次に向かっていったということですよね。

広石:これが、4枚目をリリースする時は、バンドの内部が崩壊していました…。ある日、佐久間さんにスタジオ内の別室に呼び出されて「広石、UP-BEATは解散したほうがいい。広石はソロになるなり、凡は元気いいから広石と凡で新たに始めるとか考えた方がいい、このバンドはもう終わってる。」と言われたんです。
― 佐久間さんは分かっていた。広石さんも気づいていたと。
広石:なんとなく…。それぞれの未来の自分というものが見え始めたんだと思います。
― ひとつの完成された形があると、それを繰り返すわけにはいかないですよね。次の方向性を見なくちゃいけない時、同じ方向に向かっていなかったということですか?
広石:そういうことです。
― その後のメンバーの脱退については、広石さんの中でショックはありましたか?
広石:ベースの水江(慎一郎)に関しては音楽的傾向の不一致でした。僕の望むベーススタイルと彼が望むベーススタイルが違っていた。 色々話して「じゃあ、もう一緒に出来ないね」ってスタジオで話して脱退が決まりました。
東川(真二)は辞めるとか言ってなくて、二人が在籍した最後のシングル「Rainy Valentine」のキャンペーンも一緒に行くはずだったんです。でもその頃から東川は具合が悪くて来ないときも増えて。そうこうしているうちに「UP-BEATという船は俺がいなくても進んでいくよ」なんて言うようになって。彼の中にどんな思いがあったのか分からないんですが、最終的に脱退となってしまって…。その時点でもう解散しようかな?と考えた事もありました。
だけど、そのタイミングでホッピーさんがプロデューサーとして戻ってきてくれて。ホッピーさんはUP-BEATの状況を知っていたからか、リハーサルスタジオに現れて開口一番「くよくよしてる場合か!そういう気持ちはパワーにもなるんだよ!」と激を飛ばしてくださって僕らの気分をアンダーからアッパーに変えてくれました。更にはベースを弾いて欲しいとお願いしていた佐久間さんにもご快諾頂いて。そんな流れで残った僕ら三人と、ホッピーさん、佐久間さんの五人で「ブリティッシュを思いっきりやろう!!」となったのが『Weeds & Flowers』でした。
― ものすごいロックなアルバムですよね。迷いがないように感じました。
広石:デモテープ作りに合宿したりと、すごい意欲がありましたね。
― ロックバンドのあるべき姿に感じました。不要なものを削ぎ落していった新生のUP-BEATだったなと。
広石:ありがとうございます。あのアルバムはロンドン・レコーディングというのもあるし、ある種、演劇みたいな作りにしたかったんです。
一人の少年が目覚めるところから始まって、外は狂気の世界だったり、壁に閉じこもったり。そして最後はその訳の分からない状況から抜けて成長して、巣立っていく、という映像が頭の中にあって、そういう風に作ろうとしたアルバムです。
言ってしまえばTHE WHOのロックオペラ『Tommy』ですからね。『ロッキー・ホラー・ショー』だし。イギリスでは今もずーっと続いてるあの感じです。
― そうしたコンセプトもデビュー前にビデオテープを送るというアクションから繋がっていますよね。
広石:子供の頃からなんですけど、映像でイメージするんですね。「バンドはギタリスト2人じゃないと嫌だ」とか。「遠くへ届く曲」だとか、イメージがあるんですよね。こう観えたという。

― UP-BEATは3人になってからイメージが大きくなっていますよね。
広石:そうですね。どんどん大きくなっていきましたね。『Big Thrill』の頃は岩永がすごく意見を出すようになって。彼はアメリカンが好きなんですよ。僕はアメリカンじゃないから『Weeds & Flowers』を出した後、3人でミーティングたんです。解散するか、続けるかという。
その時、「俺はブルース・スプリングスティーンとか全然ダメだからね。どっちかというと、化粧してるキュアーとかと同じと思ってくれ」と話したら、岩永は「俺はすでに(広石を)選んでいるつもりだ」って言ったので、じゃあ続けようってなったんですけど、デモテープ作りの時にスプリングスティーンの「明日なき暴走(原題:Born to Run)」そっくりの曲を作ってきて。それで仮タイトルが「Born To Free」って言うから、俺ひっくり返っちゃって(笑)。これは困ったぞと思って。それでも継続を決めたからには止まれない。だからデヴィッド・ボウイがブリティッシュな『ジギー・スターダスト』の次に『アラジン・セイン』を出してすごいアメリカンになっていきましたよね。じゃあ、その感じでやってみようかなと。
― 『Big Thrill』にはアメリカンロックも感じたし、サイケデリックの要素も感じました。バンドとしての幹を太くするためにはアメリカンな要素が不可欠だったのかなと思いました。
広石:自然とそうなったんですけどね。岩永の路線に対して僕がニューウェイブの要素を足して形にしていったわけです。
アルバムが完成するまで、僕と岩永はバチバチしてたわけで、それでタイトルが『Big Thrill』になったんです。プロデューサーだったホッピーさんもブリティッシュバリバリの方だし、かなり苦労されたと思います。
― UP-BEATの音楽って様々な要素を織り混ぜながらも、日本のメロディ、日本のバンドという部分も強いですよね。そこが支持されたひとつの理由であるとも思います。広石さんのメロディにはインパクトがありました。
広石さんは、解散後もup-beat tribute bandと名前を引き継いでいましよね。UP-BEATがご自身の生き方になっていると思います。メンバーが3人になってからの活動期間は5年ぐらいですよね。
広石:3人時代の方が長いんですよね。『GOLDEN GATE』というアルバムの頃は相変わらず岩永がアメリカ指向が強かったから、僕自身もアメリカンなものを書いてみようと思って。どうせなら岩永も黙らせるようなアメリカンな曲を書こうと。完全ブルースの曲とか、完全に乾いた感じの曲を作ったんです。「LAW GAME」と「GOLDEN GATE」はすごい悔しがってたかな。ああいうタイプの曲を彼も作りたかったんですよ。

― 90年代のUP-BEATというのは、広石さんにとって、どのようなものでしたか?
広石:一時マネジメント事務所もなくなりましたし。『GOLDEN GATE』って事務所のないアルバムなんですよ。その後、運よく事務所が決まったんですけど、これも不思議な事に大澤誉志幸さんと同じ事務所なんですよ、奇妙なご縁だと思いました。
その後にリリースした『Pleasure Pleasure』というアルバムは、プロデューサーがファーストのエンジニアだった井上剛さんになりました。音がものすごく良いし方だし、ファースト当時僕らに凄く厳しい人だったんで井上さんがいいかなと思って井上さんにお願いしました。そして最初のミーティングの時に井上さんから、「『Big Thrill』と『GOLDEN GATE』は違うんじゃないか?UP-BEATっぽくない」と言われてそれ以前の感じに戻そうみたいな話になりました。でも、あの2枚のアルバムでしっかりとアメリカを通ったことで、新しい曲たちの曲調が凄く幅広くなってたんです。
― 普通考えられないようなジャンルが混ざっているのに統一感を感じるのはUP-BEATのマジックだと思いました。
広石:『Pleasure Pleasure』はファーストの『IMAGE』を僕ら自身の手で作ったようなアルバムだと思っています。そこである意味到達したんだと思います。
― バンドらしい成長だと思います。ここで広石さん自身が生涯音楽を続けていく下地が出来たということですよね。
時代の流れの中でバンド立ち位置が変わってきたというのはありましたか?
広石:『Pleasure Pleasure』の頃は、割と楽しめていたかな。このアルバムがリリースされた93年に日清パワーステーションで動員記録を作ったライブがあったんですけど、その映像を今見ると、ものすごい楽しんでいるんですよね。僕自身が。このあたりから初めて自信が持てたんだと思います。
― しかし、そこから解散に向かっていくわけですよね。
広石:解散しようとは思ってなかった。急に壊れちゃっただけで。岩永の体調も問題もあって…。続けたいけど、もう無理だよね…と。最後のアルバム『NAKED』は「どこまでハードにやれるか」という明確なテーマがありました。ハードロックバンドではなかったけどUP-BEATなりのハードを追求しようと。日本の音楽って売ることを考えたらよりポップになっていきますよね。でも僕はどうも天邪鬼というか、逆に行ってしまう。そういう部分でも納得いくものが出来ました。ちなみに「アルバムタイトルは『NAKED』がいいんじゃないか?」と言ったのは岩永でそのままタイトルになりました。彼自身が当時NAKEDな状態だったんだと思います。
その後も実は次のアルバム用の曲も作っていて、デモテープを録ろうという段階でバンドは解散という形になりました。その後の僕のソロでは、『NAKED』のハードな部分は残しながら、ポップな要素を加味した方向になってます。その当時に作った曲たちは今もソロでやっていますから、もしバンドが続いてたらUP-BEATの次作は僕のソロ作品のような感じに近かったんじゃないかと思います。
― 解散してソロになってもバンドで培ったものが生きて、それが継続されているということですね。
広石:僕は、どこか人と違っていたいという思いが強い人間で、歌詞でも「GOLDEN GATE」の中では、「標識(しるし)まだない荒野目指す 踏みならされた道に答えはない」と書いてます。だから、誰かの作ったレールの上を走るのを嫌っている人間だと思うんです。デビュー前から、そういう行動をしているんです。「あなたたちがこうやろうとしているのが嫌だ!そんなレール乗りたくない」と。ずっとそうやってきました。
先日GLAYのドラムをやっている永井(利光)さんと一緒にあるイベントに出た時にこんな会話をしました。「僕のファンクラブ内にある、ファンの方から僕へ直接メールが届くフォームがあるんですけど、そのメールでTAKURO君がインタビューで僕の事を話してると。Webで読めるからって教えていただいて見に行ったんですよ。」と。
GLAYの曲作りの特徴についての話なんですけど、TAKURO君がインタビュー内で「美メロの曲に残酷な歌詞を乗せるのは80年代にUP-BEATの広石武彦さんなどから学びました。」と言ってくれていて本当に嬉しかったです。僕は誰の敷いたレールにも乗らなかったけど、そんな僕の敷いたレールには乗ってくれている人がいるんだって。
僕の歌詞って基本的に負け犬なんですよ。「Weeds & Flowers ~最後の国境~」で「本当は負け犬さ 遠吠えも弱い」ってちゃんと書いたし。だけど「逃げ惑うNameless fowers 名もない花よ 時代の仕打ちに咲いて見せろ The unknown weeds 知れない雑草たちよ 踏まれた大地で空を指せ」とも書いています。
デビュー前にコテンパンに負けて、そこから始まっているんです。負けてるヤツが、それでも… って続いていった。それがUP-BEATなんです。
(インタビュー・構成 / 本田隆)
3回に渡ってお届けしたUP-BEAT広石武彦インタビュー、いかがでしたでしょうか? 煌びやかなバンドサウンドに隠された苦悩と、日本の音楽シーンに色鮮やかに残したUP-BEATの軌跡…。“孤高のロックバンド”たる所以を存分に感じ取っていただけたと思います。
2022.05.01
僕の歌詞は基本 “負け犬” 負けてるヤツが、それでも…って続いていった。それがUP-BEAT
松本隆監督作品「微熱少年」に出演
― 広石さんは映画、松本隆さんの『微熱少年』にも出演されていますよね。
広石:松本隆さんには「この映画に出演する役者は本当のミュージシャンでなければならない」というこだわりがあって、当時数多く発行されていた邦楽の音楽雑誌をチェックしたなかで僕の目が良いって、気に入って下さったらしくて。それでお会いして話したんですが、キャスティング自体は当時の事務所が主導して決めたことで、僕は出演がすでに決まっていたことを知りませんでした。松本さんが帰ってからの助監督さんとの打ち合わせで「あ、俺この映画に出るんだ」と気付いたくらいです。だけど、受けたからには一生懸命やりましたよ。それにあの映画に出演したおかげで松田聖子さんに楽曲提供することもできましたし。「チャンスは2度ないのよ」という曲です。
― 今のお話を聞いていて、売れることは確かに大事で、そのために事務所も試行錯誤しつつ…。
広石:『微熱少年』はファーストの頃だから、いろんなことがありましたよ。誰も焦点が定まってない時期でした。そこを是永さんがまとめてくれたのがファーストアルバムです。だけど、僕らが演奏しているわけじゃないから『IMAGE』というタイトルにしました。これはUP-BEATのイメージだからと。そこから、「俺たち進歩していこうぜ!」ってガツンと。
バンドは”虫メガネ”
― その時、メンバー5人が一枚岩で向かっていく感じでしたか?
広石:だんだんそうなっていく感じでした。だけど、UP-BEATは最後まで完全な一枚岩ではなかったです。僕が強引に引っ張ってました。
― 僕も広石さんのイニシアチブをなんとなく分かってはいました。それでもメンバーと見ているところが違うと、バンド継続が難しい部分があると思いますが。
広石:メンバー全員が同じ方向を見ているという、僕の思い込みが強かったんだと思います。
― 広石さんの中で、こういうバンドを目指そう、こういう風になるためには、ここと、ここが必要だよっていうところが実は違っていたと。それに気づいたのはいつぐらいですか?
広石:僕がインタビューでよく話す例えですが、「バンドっていうのは虫メガネみたいなものだよ」と。虫メガネというのは、光を一点に集中して集めると、なんだって焦がして、最後は突き抜けていっちゃうじゃないですか。これがバンドなんです。でも見ている向きが違う人たちに話しても、その人の心に響くかどうかは分からないですよね。だけど、僕はメンバーに一方的にそういうことを言ってました。
― 広石さんには意地もあったと思うし、どんどん良いアルバムを出していきますよね。音楽性が深化していく中にもバンドとして変わらないスタンスもある。広石さんの存在感もずっと変わらなかったと思います。
広石:セカンドのレコーディングが終わって、僕はかなり無理をしていたんでしょうね。全然曲が書けなくなりました。そのタイミングでディレクターが変わったんですがその新しいディレクターの方が僕を休ませてくれたんです。「レコーディングが止まってもいいから、何か月か休んでいいよ」と。あれは本当にありがたかったです。
― UP-BEATがデビューしてから長い期間、それだけ真正面から向き合っていれば心労も相当だったと思います。
広石:心労すごかったですよ。毎日あんまり面白くないですよね(笑)。
― ライブとかはどうでした。熱狂するファンも多かったと思いますが。
広石:僕自身完成していなかったし、自分の歌唱にも自信を持てていなかったから、疑心暗鬼になっていましたね。一生懸命やっているんだけど、良かったのかどうなのか分からない。ずっともがいてる感じでした。でも、何故今みたいに歌えなかったのか?と考えてもわからないんです。
― 今が一番いいということですね。
広石:多分そうです。
デジタルリマスターで蘇るUP-BEAT
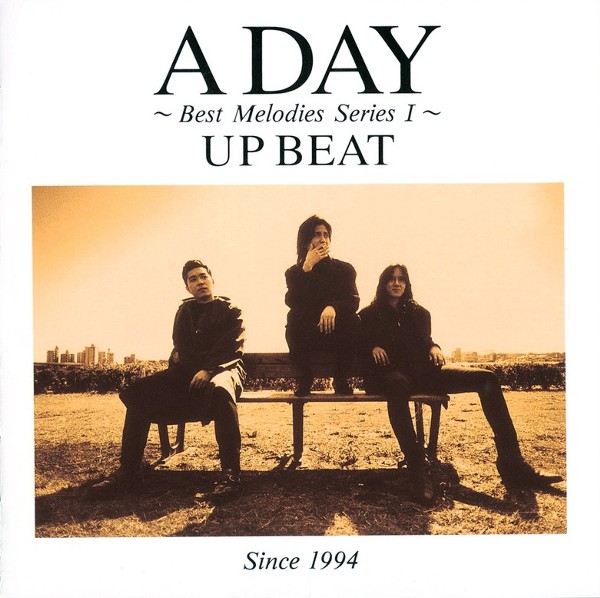
― 今回は、シングルのコンプリートがリマスターでリリースされますが、リリース順にお聴きになってどうですか?
広石:僕自身の後からの目線だと全部惜しいんですよ。あと少しが足りない…。歌にしても何にしても。過去に一回だけ、「Sister Tomorrow –Still I Miss You-」というシングル曲をやり直したことがあるんですよ。(註:ミニアルバム『A DAY』でリメイク収録した)
これは僕の中で完璧な出来なんですね。何故それが、最初に出来なかったのかと考えると、疲れてたんです。いざ歌う最後の段の時にそれまでの作業によって、ヘトヘトになっているんです。レコーディングはそんな感じで疲れている分、本人的には突き抜けていない印象を持ってしまうというか…。
― 意外ですね。これだけ煌びやかな世界を作り上げているのに、その中でも苦悩があったんですね。しかし今回のマスタリングで変わって聴こえてくる部分もありますよね。
広石:魔法ですね! マスタリングエンジニアの方は素晴らしいです!
― UP-BEATのようなバンドはシングルコンプリートで出す意義がすごく大きいと思います。バンドの変化が見えるじゃないですか。
広石:シングルだけは、シングルっぽく作らなきゃと思っていました。だからUP-BEATってアルバムを聴くと評価が変わると思います。
― シングルは幅広い層に届けるためにということですね。
広石:そうです。佐久間さんの対応もセカンド以降は真逆になっていくんです。自分たちはライブもやって、ツアーもこなして普通に上手くなっていました。すると、セカンドであれだけ厳しかった佐久間さんが「間違っていることは僕が正すからそれ以外は好きにやりなさい」と。それが『HERMIT COMPLEX』でした。

― ここでUP-BEATらしさを全面に出せたと。
広石:ギターの岩永(凡)らしさを初めて出せたのが『HERMIT COMPLEX』だと思います。骨太いバンドっぽくしたかったんです。そう思っていた時期に佐久間さんは好きにやらせてくれて。
― そこでバンドのグルーヴをしっかり出せて、次に向かっていったということですよね。
バンドの崩壊、そしてメンバーの脱退…

広石:これが、4枚目をリリースする時は、バンドの内部が崩壊していました…。ある日、佐久間さんにスタジオ内の別室に呼び出されて「広石、UP-BEATは解散したほうがいい。広石はソロになるなり、凡は元気いいから広石と凡で新たに始めるとか考えた方がいい、このバンドはもう終わってる。」と言われたんです。
― 佐久間さんは分かっていた。広石さんも気づいていたと。
広石:なんとなく…。それぞれの未来の自分というものが見え始めたんだと思います。
― ひとつの完成された形があると、それを繰り返すわけにはいかないですよね。次の方向性を見なくちゃいけない時、同じ方向に向かっていなかったということですか?
広石:そういうことです。
― その後のメンバーの脱退については、広石さんの中でショックはありましたか?
広石:ベースの水江(慎一郎)に関しては音楽的傾向の不一致でした。僕の望むベーススタイルと彼が望むベーススタイルが違っていた。 色々話して「じゃあ、もう一緒に出来ないね」ってスタジオで話して脱退が決まりました。
東川(真二)は辞めるとか言ってなくて、二人が在籍した最後のシングル「Rainy Valentine」のキャンペーンも一緒に行くはずだったんです。でもその頃から東川は具合が悪くて来ないときも増えて。そうこうしているうちに「UP-BEATという船は俺がいなくても進んでいくよ」なんて言うようになって。彼の中にどんな思いがあったのか分からないんですが、最終的に脱退となってしまって…。その時点でもう解散しようかな?と考えた事もありました。
だけど、そのタイミングでホッピーさんがプロデューサーとして戻ってきてくれて。ホッピーさんはUP-BEATの状況を知っていたからか、リハーサルスタジオに現れて開口一番「くよくよしてる場合か!そういう気持ちはパワーにもなるんだよ!」と激を飛ばしてくださって僕らの気分をアンダーからアッパーに変えてくれました。更にはベースを弾いて欲しいとお願いしていた佐久間さんにもご快諾頂いて。そんな流れで残った僕ら三人と、ホッピーさん、佐久間さんの五人で「ブリティッシュを思いっきりやろう!!」となったのが『Weeds & Flowers』でした。
― ものすごいロックなアルバムですよね。迷いがないように感じました。
広石:デモテープ作りに合宿したりと、すごい意欲がありましたね。
― ロックバンドのあるべき姿に感じました。不要なものを削ぎ落していった新生のUP-BEATだったなと。
広石:ありがとうございます。あのアルバムはロンドン・レコーディングというのもあるし、ある種、演劇みたいな作りにしたかったんです。
一人の少年が目覚めるところから始まって、外は狂気の世界だったり、壁に閉じこもったり。そして最後はその訳の分からない状況から抜けて成長して、巣立っていく、という映像が頭の中にあって、そういう風に作ろうとしたアルバムです。
言ってしまえばTHE WHOのロックオペラ『Tommy』ですからね。『ロッキー・ホラー・ショー』だし。イギリスでは今もずーっと続いてるあの感じです。
― そうしたコンセプトもデビュー前にビデオテープを送るというアクションから繋がっていますよね。
広石:子供の頃からなんですけど、映像でイメージするんですね。「バンドはギタリスト2人じゃないと嫌だ」とか。「遠くへ届く曲」だとか、イメージがあるんですよね。こう観えたという。
3人になってからのUP-BEAT、壮大な世界観

― UP-BEATは3人になってからイメージが大きくなっていますよね。
広石:そうですね。どんどん大きくなっていきましたね。『Big Thrill』の頃は岩永がすごく意見を出すようになって。彼はアメリカンが好きなんですよ。僕はアメリカンじゃないから『Weeds & Flowers』を出した後、3人でミーティングたんです。解散するか、続けるかという。
その時、「俺はブルース・スプリングスティーンとか全然ダメだからね。どっちかというと、化粧してるキュアーとかと同じと思ってくれ」と話したら、岩永は「俺はすでに(広石を)選んでいるつもりだ」って言ったので、じゃあ続けようってなったんですけど、デモテープ作りの時にスプリングスティーンの「明日なき暴走(原題:Born to Run)」そっくりの曲を作ってきて。それで仮タイトルが「Born To Free」って言うから、俺ひっくり返っちゃって(笑)。これは困ったぞと思って。それでも継続を決めたからには止まれない。だからデヴィッド・ボウイがブリティッシュな『ジギー・スターダスト』の次に『アラジン・セイン』を出してすごいアメリカンになっていきましたよね。じゃあ、その感じでやってみようかなと。
― 『Big Thrill』にはアメリカンロックも感じたし、サイケデリックの要素も感じました。バンドとしての幹を太くするためにはアメリカンな要素が不可欠だったのかなと思いました。
広石:自然とそうなったんですけどね。岩永の路線に対して僕がニューウェイブの要素を足して形にしていったわけです。
アルバムが完成するまで、僕と岩永はバチバチしてたわけで、それでタイトルが『Big Thrill』になったんです。プロデューサーだったホッピーさんもブリティッシュバリバリの方だし、かなり苦労されたと思います。
― UP-BEATの音楽って様々な要素を織り混ぜながらも、日本のメロディ、日本のバンドという部分も強いですよね。そこが支持されたひとつの理由であるとも思います。広石さんのメロディにはインパクトがありました。
広石さんは、解散後もup-beat tribute bandと名前を引き継いでいましよね。UP-BEATがご自身の生き方になっていると思います。メンバーが3人になってからの活動期間は5年ぐらいですよね。
広石:3人時代の方が長いんですよね。『GOLDEN GATE』というアルバムの頃は相変わらず岩永がアメリカ指向が強かったから、僕自身もアメリカンなものを書いてみようと思って。どうせなら岩永も黙らせるようなアメリカンな曲を書こうと。完全ブルースの曲とか、完全に乾いた感じの曲を作ったんです。「LAW GAME」と「GOLDEN GATE」はすごい悔しがってたかな。ああいうタイプの曲を彼も作りたかったんですよ。
90年代のUP-BEAT、到達点の「Pleasure Pleasure」

― 90年代のUP-BEATというのは、広石さんにとって、どのようなものでしたか?
広石:一時マネジメント事務所もなくなりましたし。『GOLDEN GATE』って事務所のないアルバムなんですよ。その後、運よく事務所が決まったんですけど、これも不思議な事に大澤誉志幸さんと同じ事務所なんですよ、奇妙なご縁だと思いました。
その後にリリースした『Pleasure Pleasure』というアルバムは、プロデューサーがファーストのエンジニアだった井上剛さんになりました。音がものすごく良いし方だし、ファースト当時僕らに凄く厳しい人だったんで井上さんがいいかなと思って井上さんにお願いしました。そして最初のミーティングの時に井上さんから、「『Big Thrill』と『GOLDEN GATE』は違うんじゃないか?UP-BEATっぽくない」と言われてそれ以前の感じに戻そうみたいな話になりました。でも、あの2枚のアルバムでしっかりとアメリカを通ったことで、新しい曲たちの曲調が凄く幅広くなってたんです。
― 普通考えられないようなジャンルが混ざっているのに統一感を感じるのはUP-BEATのマジックだと思いました。
広石:『Pleasure Pleasure』はファーストの『IMAGE』を僕ら自身の手で作ったようなアルバムだと思っています。そこである意味到達したんだと思います。
― バンドらしい成長だと思います。ここで広石さん自身が生涯音楽を続けていく下地が出来たということですよね。
時代の流れの中でバンド立ち位置が変わってきたというのはありましたか?
広石:『Pleasure Pleasure』の頃は、割と楽しめていたかな。このアルバムがリリースされた93年に日清パワーステーションで動員記録を作ったライブがあったんですけど、その映像を今見ると、ものすごい楽しんでいるんですよね。僕自身が。このあたりから初めて自信が持てたんだと思います。
“負け犬”UP-BEATが敷いたレールと後進のバンドに及ぼした大きな影響
― しかし、そこから解散に向かっていくわけですよね。
広石:解散しようとは思ってなかった。急に壊れちゃっただけで。岩永の体調も問題もあって…。続けたいけど、もう無理だよね…と。最後のアルバム『NAKED』は「どこまでハードにやれるか」という明確なテーマがありました。ハードロックバンドではなかったけどUP-BEATなりのハードを追求しようと。日本の音楽って売ることを考えたらよりポップになっていきますよね。でも僕はどうも天邪鬼というか、逆に行ってしまう。そういう部分でも納得いくものが出来ました。ちなみに「アルバムタイトルは『NAKED』がいいんじゃないか?」と言ったのは岩永でそのままタイトルになりました。彼自身が当時NAKEDな状態だったんだと思います。
その後も実は次のアルバム用の曲も作っていて、デモテープを録ろうという段階でバンドは解散という形になりました。その後の僕のソロでは、『NAKED』のハードな部分は残しながら、ポップな要素を加味した方向になってます。その当時に作った曲たちは今もソロでやっていますから、もしバンドが続いてたらUP-BEATの次作は僕のソロ作品のような感じに近かったんじゃないかと思います。
― 解散してソロになってもバンドで培ったものが生きて、それが継続されているということですね。
広石:僕は、どこか人と違っていたいという思いが強い人間で、歌詞でも「GOLDEN GATE」の中では、「標識(しるし)まだない荒野目指す 踏みならされた道に答えはない」と書いてます。だから、誰かの作ったレールの上を走るのを嫌っている人間だと思うんです。デビュー前から、そういう行動をしているんです。「あなたたちがこうやろうとしているのが嫌だ!そんなレール乗りたくない」と。ずっとそうやってきました。
先日GLAYのドラムをやっている永井(利光)さんと一緒にあるイベントに出た時にこんな会話をしました。「僕のファンクラブ内にある、ファンの方から僕へ直接メールが届くフォームがあるんですけど、そのメールでTAKURO君がインタビューで僕の事を話してると。Webで読めるからって教えていただいて見に行ったんですよ。」と。
GLAYの曲作りの特徴についての話なんですけど、TAKURO君がインタビュー内で「美メロの曲に残酷な歌詞を乗せるのは80年代にUP-BEATの広石武彦さんなどから学びました。」と言ってくれていて本当に嬉しかったです。僕は誰の敷いたレールにも乗らなかったけど、そんな僕の敷いたレールには乗ってくれている人がいるんだって。
僕の歌詞って基本的に負け犬なんですよ。「Weeds & Flowers ~最後の国境~」で「本当は負け犬さ 遠吠えも弱い」ってちゃんと書いたし。だけど「逃げ惑うNameless fowers 名もない花よ 時代の仕打ちに咲いて見せろ The unknown weeds 知れない雑草たちよ 踏まれた大地で空を指せ」とも書いています。
デビュー前にコテンパンに負けて、そこから始まっているんです。負けてるヤツが、それでも… って続いていった。それがUP-BEATなんです。
(インタビュー・構成 / 本田隆)
3回に渡ってお届けしたUP-BEAT広石武彦インタビュー、いかがでしたでしょうか? 煌びやかなバンドサウンドに隠された苦悩と、日本の音楽シーンに色鮮やかに残したUP-BEATの軌跡…。“孤高のロックバンド”たる所以を存分に感じ取っていただけたと思います。
2022.05.01
Songlink
Information
あなた

























