この日何の日?
ジョージ・ハリスンのベストアルバム「レット・イット・ロール ソングス・オブ・ジョージ・ハリスン」がリリースされた日
この時あなたは
0歳
無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます
2009年のコラム
令和も生き続けるロックシンガー【川村カオリ】屈せず、媚びず、自らの場所を探しながら…
ミュージカルTVドラマ「glee/グリー」で蘇った80年代の名曲たち
川村カオリ ― 全身で音楽を呼吸し続けたロックンローラー
もっとみる≫
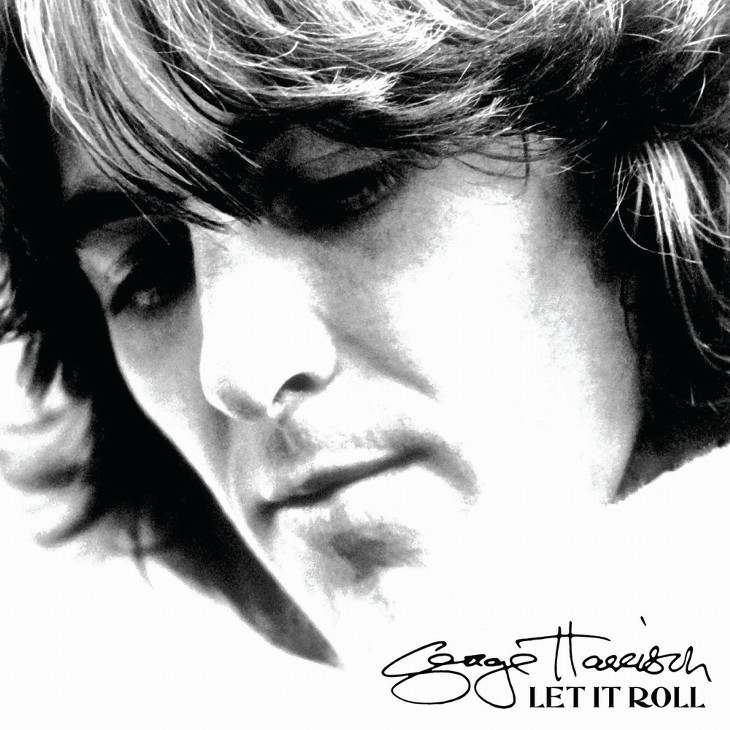
11月29日はジョージ・ハリスンの命日
2001年11月29日、ジョージ・ハリスンが癌のために58歳という若さでこの世を去った。
当然だけれど、ジョージ・ハリスンを知ったのはビートルズのメンバーとしてだった。もし、バンドのリードギタリストが花形となっていたもう少し後の時代にビートルズが登場していたら、ジョージはもっと脚光を浴びていたかもしれないとも思う。けれど、ビートルズがデビューした頃は、演奏しながら歌うバンドというスタイルそのものが珍しく感じられたものの、具体的な演奏テクニックにまで関心を抱くことはそれほど無かったという気がする。もちろんそれは、ガキだった自分が、まだバンドの知識も経験もまったく無かったからなのだけれど…。
そんな僕たちが感心していたのは、ビートルズのレパートリーの多くがメンバーが書いたオリジナル曲だったということで、その意味ではやはりジョン・レノンとポール・マッカートニーの存在感が圧倒的だった。
当時のジョージ・ハリスンは、メンバー最年少ということもあったのか、まさに “静かなるビートルズ” と言われるにふさわしい、メンバーの中では一歩引いた目立たない存在という印象があった。
インド音楽に傾倒していったジョージ・ハリスン
ビートルズの中でジョージ・ハリスンの存在感がクローズアップされてきたのは、1966年頃からのインド音楽に傾倒していった時期からだったんじゃないかと思う。
高名なシタール奏者ラヴィ・シャンカルの手ほどきを受けて吸収したインド音楽のメソッドを生かし、アルバム『リボルバー』(1965年)にインド楽器を使った「ラブ・ユー・トゥ」を入れるなど、ロックとインド音楽のフュージョン(融合)にトライするなど、ビートルズの音楽性を広げ、進化させていこうとする動きを、ジョンやポールとは違う形で示していくようになった。
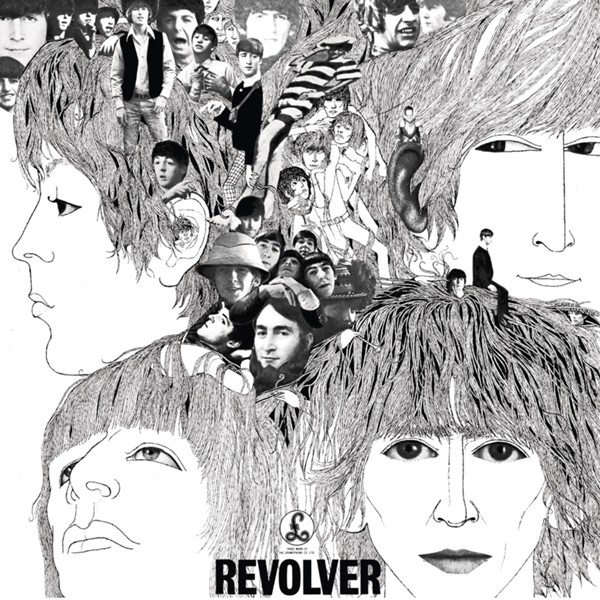
当時の僕は、ビートルズとインド音楽という顔合わせに、それまでまったく接点が無かった西洋文化と東洋文化の出逢い、というナイーブなロマンティシズムを感じたりもしていた。ちょっと考えてみれば、イギリスとインドの間にはかなり深い歴史的な因縁があることはすぐわかるハズだったし、その文脈にジョージ・ハリスンのインド音楽、およびインド哲学への傾倒を重ねてみれば、それが単なる音楽ジャンルの出来事に止まるのではなく、かつての植民地と宗主国との間の価値観の転換を暗示する動きでもあったことも想像できたろうと思う。
しかも、そんなイギリスとインドを含む旧植民地との関係性は、その前に観ていたビートルズ映画『ヘルプ~四人はアイドル』(1965年)にもしっかりと描かれていたのだけれど、僕がそんな背景に気づいたのは、ずいぶん経ってからのことだった。
ソングライターとしてのジョージ・ハリスンの力量も、レノン=マッカートニーの陰に隠れて過小評価されてきたと思う。
ジョージ・ハリスンの印象が大きく変わった「ホワイト・アルバム」
初期のジョージ・ハリスンは『ウイズ・ザ・ビートルズ』(1963年)の「ドント・バザー・ミー」を皮切りに、『ヘルプ! 四人はアイドル』以降のアルバムに2〜3曲の楽曲を提供している。ちょっとトリッキーな面白さもあるけれど、強烈な個性や自己主張を見せるというよりも、アルバムのなかでやや控えめにアクセントとなっている楽曲という印象があった。
そんな先入観が大きく変わったのが、1968年にリリースされた『ザ・ビートルズ』(ホワイト・アルバム)に収められていた「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」「ピッギーズ」「ロング・ロング・ロング」「サボイ・トラッフル」の4曲だった。
4曲ともタイプは違うが、どれも複雑なモチーフを巧みに組み合わせて構成された個性あふれる楽曲で、サウンド的にもビートルズのメンバーだけの演奏にこだわらない大胆な編成でダイナミックに構築されている。そしてこれらの楽曲は、2枚組というボリュームの『ザ・ビートルズ』(ホワイト・アルバム)のなかでもきわめて魅力的なトラックで、まさな覚睡したジョージ・ハリスンがここに居る、という鮮烈な印象があった。
『ザ・ビートルズ』(ホワイト・アルバム)で見せたソングライターとしての輝きは、『アビイ・ロード』(1969年)の「サムシング」「ヒア・カム・ザ・サン」でも遺憾なく発揮されていた。しかし、もっとも輝かしいモニュメントになったのは、ビートルズ解散後に発表されたソロアルバム『オール・シングス・マスト・パス』(1970年)と言っていいのではないかと思う。

ジョージ・ハリスン、ソロ曲としての代表「マイ・スウィート・ロード」、「美しき人生」
ジョージ・ハリスンのソロ曲としての代表と言える「マイ・スウィート・ロード」「美しき人生」などを含む3枚組23曲という大作をビートルズ解散直後に発表することができたのは、発表の機会はあまり無かったものの、ビートルズ時代に精力的に楽曲を作り続けていたからなのではないかと推測できる。
もうひとつ、ビートルズ時代のジョージ・ハリスンの音楽活動で印象的だったのが、いち早くエレクトロニクス・サウンドに取り組んだことだ。1969年、ジョージ・ハリスンは、ビートルズが設立したレコード会社アップルから『電子音楽の世界』というシンセサイザーによる現代音楽に通じる前衛的アルバムを発表している。
当時、インド音楽へのアプローチもポップスのクリエイティブとは逆行するものと受け取られていたが、このあまりに早すぎたエレクトロニクス・ミュージックへの挑戦は、それ以上に無謀な行動と見られていた。
しかし、この無謀とも思える先進性もまた、ジョージ・ハリスンの一面だった。

“静かなるビートルズ” のイメージからは想像もできない行動力
改めてジョージ・ハリスンについて振り返ってみて思い浮かぶのは、ジョン・レノンの強烈なメッセージ表現の陰に隠れてあまり目立たなかったけれど、ジョージ・ハリスンも実は強い社会意識を持ち、実際に表現をしていたということだ。
例えばアルバム『ラバーソウル』(1965年)に収められている「嘘つき女」も政治的な暗喩が込められているという解釈もあるし、『リボルバー』(1966年)の「タックスマン」は自分たちに課せられている税金の高さに対する問題提起の曲だった。さらに『ザ・ビートルズ』(ホワイト・アルバム)の「ピッギーズ」も階級社会をテーマにしている。これ以外にもジョージ・ハリスンの曲には、哲学や宗教観、そして人としての生き方をテーマとしたものが多い。
そうした彼の社会的な意識は音楽表現だけでなく、行動からも見てとることができる。たとえば1971年8月1日にニューヨークのマジソン・スクエア・ガーデンで行われたバングラデシュ難民救済のためのチャリティコンサート『バングラデシュ救済コンサート』も、ジョージ・ハリスンならではのイベントだった。
ラヴィ・シャンカルから伝えられたバングラデシュの惨状に対して、ボブ・ディラン、レオン・ラッセル、エリック・クラプトン、リンゴ・スター、バッド・フィンガーなどの豪華メンバーによるチャリティ・コンサートを実現させ、このコンサートのためにシングル「バングラデシュ」をリリースするという、かつての “静かなるビートルズ” のイメージからは想像もできない行動力を発揮している。
ちなみにこの『バングラデシュ救済コンサート』のライブアルバム『バングラデシュ・コンサート』(1971年)は1972年のグラミー賞で最優秀アルバム賞を受賞している名盤だ。

1980年以降のジョージ・ハリスンの注目すべき動き
ジョージ・ハリスンがこうした行動力を見せることができた背景には、その交友関係の広さもあっただろう。ビートルズ時代からのエリック・クラプトンとの交流は、「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」のリード・ギターをエリック・クラプトンに弾かせたというエピソードにも見られるほど有名だし、ビートルズ晩年のドキュメント映画『レット・イット・ビー』(1970年)ともなった、いわゆる “ゲット・バック・セッション” にキーボード奏者のビリー・プレストンを参加させたのもジョージ・ハリスンだった。
ラヴィ・シャンカルとの交流は『バングラデシュ救済コンサート』後も続き、1997年にはジョージ・ハリスンがラヴィ・シャンカルのアルバムをプロデュースしているし、2002年に行われたジョージ・ハリスンの追悼コンサートにもラヴィ・シャンカルは参加している。
1980年代以降、ジョージ・ハリスンの音楽活動はあまり目立たないものになっていく。それでも、エレクトリック・ライト・オーケストラのジェフ・リンとの出会いによってアルバム『クラウド・ナイン』(1987年)をヒットさせたり、トラべリン・ウィルベリーズ(ジョージ・ハリスン、ボブ・ディラン、ロイ・オービソン、トム・ベティ、ジェフ・リンというスーパースターによって1988年に結成された覆面バンド)などの注目すべき動きを見せていった。
ジョージ・ハリスンの音楽は、今でも心に響くインパクトを持っている。それだけに、その幅広い人脈と彼ならではの音楽性を生かした活動が、さらに続いていたら生まれたかもしれない新しいクリエイティビティを感じてみたかったと、ふとも思ったりもする。

アナタにおすすめのコラム
2022.11.29
Songlink
Information
あなた
























