この日何の日?
マイケル・フランクスのアルバム「スリーピング・ジプシー」がリリースされた時期
この時あなたは
0歳
無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます
1977年のコラム
かまやつひろし「ニューミュージック・ベストテン」それってフォーク? 歌謡曲?
50'sブームとは?アメリカに未来を見いだした80年代のティーンエイジャー
ビリー・ジョエル「素顔のままで」略奪愛の妻に贈ったラブソングでグラミー賞2冠!
令和に響く赤貧ソング、老後 2,000万円問題と太田裕美の「しあわせ未満」
フリートウッド・マック「噂」泥沼不倫の三角関係?複雑すぎるバンド内の人間模様
80年代は洋楽黄金時代【アメリカ大統領選の音楽 TOP10】歴代キャンペーン悲喜こもごも
もっとみる≫
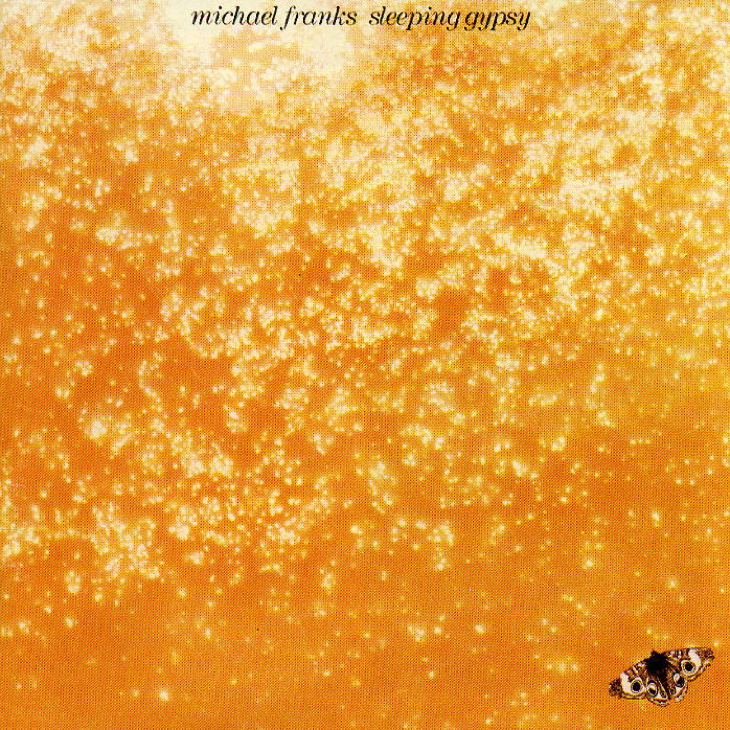
photo:Warner Music Japan
今年2018年は、ボサノバ誕生60周年であるらしい。
ブラジルの3人の奇才、ジョアン・ジルベルト<ギタリスト・歌手>、アントニオ・カルロス・ジョビン<作曲家・ピアニスト>、ヴィニシウス・ジ・モライス<詩人・作家>によるアルバム「想いあふれて(Chega De Saudade)」(1958年)をその起源としているようだ。
「ボサノバ」という言葉の由来は、新しい傾向、新しい感覚という意味のポルトガル語であるという。サンバとジャズの融合によってもたらされた、軽やかで都会的なサウンドにふさわしい、実にセンスのあるネーミングだと今更ながら思ってしまう。
今回とり上げるのは、このボサノバを音楽ルーツのひとつとする AOR 界のレジェンド、マイケル・フランクスだ。代表曲である1977年の「アントニオの歌(Antonio's Song - The Rainbow)」は、先述の作曲家、アントニオ・カルロス・ジョビンへ捧げられた歌である。
マイケル・フランクスが、ジョビンの曲に触れたのは UCLA へ通う学生時代だったという。ボサノバ史上の不朽の名作『ゲッツ / ジルベルト』が発表され、シングル「イパネマの娘(The Girl from Ipanema)」(ジョビン作曲)が全米ポップチャートにくい込むほどのインパクトを与えた頃である。
「ジョビンの音楽は、しばらく住んでみたいと思うような、別の惑星のようだった。メロディやリズムの構造が全く別のものだったんだ」(マイケル・フランクス『Anthology - The Art Of Love / アルティメイト・ベスト』ライナーノーツより)
“しばらく住んでみたい別の惑星” とは、なんと詩的な表現だろう。感受性レベルが程遠いのは承知のうえで、実は私も似たような体験をしたのだった。子供の頃に通っていたヤマハエレクトーン教室で、課題曲として「イパネマの娘」に遭遇した時のこと――
それまでコードのFといえば、足鍵盤(ルート音)=ファ、左手=ラ+ド+ファだったのが、イパネマでは、足鍵盤=ファの上に、左手=ミ+ラ+レが乗る。そして、メロディーも「ソッミミーレ ソッミッミーミレ」と、ラ・ド・ファは出てこない。さらにバッキングのリズムは、2拍4拍の裏打ちではなく、シンコペーションを刻む。これには困惑し、驚いた。
―― と同時にものすごく気持ちが良かった。しばらくは、その浮遊感あるハーモニーとさざ波のようなリズムの虜となり、先生に「もっと他にもこういうのはないのか」とオネダリをしたのを覚えている…。
そんな別惑星からの使者、ジョビンへの敬愛から生まれた「アントニオの歌」。ジャズ・フュージョン界のトップアーティストを集めた洗練のサウンドと、マイケル・フランクスの囁くような甘い歌声。それだけでも十分に魅力的なのだが、この曲を印象づけたのは、なんといってもサビのメロディー3音だろう。
But sing the Song
ド ソ# シ
(キーは Am)
伝わるだろうか、この妖艶な響き。そして、この「ドソ#シ」は、ストリングスによるカウンターメロディーの一部として、曲中で幾度も繰り返される。
ひねりのないコードでいくと E7 → Am で済むところを、このメロディー3音で Eaug7 → Am add9 を表現しているのだ。特に Am(ラ+ド+ミ)に乗るシの音、いわゆるナインス(9th)の響きが、翳りある雰囲気を醸しだし、切なげでクールなボサノバチューンとしての完成度を高めている。
こうしてボサノバ、AOR のフィーリングを絶妙にブレンドし、歌ものポップスとして耳なじみの良い仕上がりとなった「アントニオの歌」は、世界的なヒットとなり、その後多くのアーティストにカバーされた。そして、ジョビンの楽曲がマイケル・フランクスに大きな衝撃を与えたように、日本の作曲家にも大きな影響を及ぼしたと思われる。
マイナー(短調)のボサノバ調の曲に焦点を絞って、すぐに思い浮かぶのが「あの日にかえりたい」荒井由実(75年)。そして、「どうぞこのまま」丸山圭子(76年)である。なんとこの2曲は「アントニオの歌」以前のリリースだ。日本ボサノバ歌謡の先駆け、恐るべし。
振り返ると、60〜70年代のムード歌謡にも、所々に複雑なコードが見受けられる。だがそれらは、ラテンの中でもカリブ系のルンバやマンボ、チャチャチャから派生したものと思われ、ブラジル発祥のボサノバ流派とは別ものと想定される。何よりリズムがシンコペーションの「さざ波」ではない。そういった意味では、いち早くポップスにボサノバを取り入れたユーミン、丸山圭子は、実に偉大である。
そして、80年代に入ると、あの「ドソ#シ」が歌謡曲のメロディーに現れ、妖艶な響きを放ちはじめる。
テレサ・テン
「つぐない」(作曲:三木たかし / 1984)
♪ 窓に西陽が…
ミドソ#シシーララー
桑田佳祐による『3大ドソ#シ』
「私はピアノ」(1980)
♪ くりかえすのはただ lonely play
ラドレレレレミーレシー ドソ#シーラー
「匂艶THE NIGHT CLUB」(1982)
♪ 俺の Kiss は きっと痛いよ
ミレドーレミソファー レミーミドソ#シーラー
「Long-haired Lady」(1985)
♪ 波音も濡れている Hello Darkness
ドソ#シーラミー ミドソーファシー
ファミーレードー
そもそも、音数の少ないシンプルなメロディーの裏で、複雑かつ繊細なハーモニーがうごめくボサノバの曲。それに、70年代後半からの AOR 人気が後押しをして、「アントニオの歌」につづくように、日本でもボサノバフレーバーの物憂げな歌謡曲が続々と登場していった。音楽に対して「都会的」という新たな評価基準が加わったのもこの頃だろう。
最後に、ボサノバ誕生から60年、地球の裏側に思いを馳せつつ、ボサノバ歌謡創成期の超私的ベストテンを発表(今回はマイナーキーのもの限定)。のちにユーミンの「あの日にかえりたい」をカバーしているマイケル・フランクスに、できることならこれらの曲も歌って欲しいものだ。
第10位 菊池桃子「もう逢えないかもしれない」(1985)
■作編曲:林哲司
第9位 鈴木雄大「レイニーサマー」(1983)
■作編曲:都倉俊一
第8位 早見優「哀愁情句」(1984)
■作曲:筒美京平 / 編曲:船山基紀
第7位 五十嵐浩晃「愛は風まかせ」(1980)
■作曲:五十嵐浩晃 / 編曲:鈴木茂
第6位 研ナオコ「夏をあきらめて」(1982)
■作曲:桑田佳祐 / 編曲:若草恵
第5位 サーカス「Mr.サマータイム」(1978)
■作曲:Michel Fugain / 編曲:前田憲男
第4位 稲垣潤一「ドラマティック・レイン」(1982)
■作曲:筒美京平 / 編曲:船山基紀
第3位 中村雅俊「恋人も濡れる街角」(1982)
■作曲:桑田佳祐 / 編曲:桑田佳祐、八木正生
第2位 桐ヶ谷仁「さらば愛の日々」(1981)
■作曲:桐ヶ谷仁 / 編曲:松原正樹、松任谷正隆
第1位 杉山清貴&オメガトライブ「君のハートはマリンブルー」(1984)
■作編曲:林哲司
2018.09.18
ブラジルの3人の奇才、ジョアン・ジルベルト<ギタリスト・歌手>、アントニオ・カルロス・ジョビン<作曲家・ピアニスト>、ヴィニシウス・ジ・モライス<詩人・作家>によるアルバム「想いあふれて(Chega De Saudade)」(1958年)をその起源としているようだ。
「ボサノバ」という言葉の由来は、新しい傾向、新しい感覚という意味のポルトガル語であるという。サンバとジャズの融合によってもたらされた、軽やかで都会的なサウンドにふさわしい、実にセンスのあるネーミングだと今更ながら思ってしまう。
今回とり上げるのは、このボサノバを音楽ルーツのひとつとする AOR 界のレジェンド、マイケル・フランクスだ。代表曲である1977年の「アントニオの歌(Antonio's Song - The Rainbow)」は、先述の作曲家、アントニオ・カルロス・ジョビンへ捧げられた歌である。
マイケル・フランクスが、ジョビンの曲に触れたのは UCLA へ通う学生時代だったという。ボサノバ史上の不朽の名作『ゲッツ / ジルベルト』が発表され、シングル「イパネマの娘(The Girl from Ipanema)」(ジョビン作曲)が全米ポップチャートにくい込むほどのインパクトを与えた頃である。
「ジョビンの音楽は、しばらく住んでみたいと思うような、別の惑星のようだった。メロディやリズムの構造が全く別のものだったんだ」(マイケル・フランクス『Anthology - The Art Of Love / アルティメイト・ベスト』ライナーノーツより)
“しばらく住んでみたい別の惑星” とは、なんと詩的な表現だろう。感受性レベルが程遠いのは承知のうえで、実は私も似たような体験をしたのだった。子供の頃に通っていたヤマハエレクトーン教室で、課題曲として「イパネマの娘」に遭遇した時のこと――
それまでコードのFといえば、足鍵盤(ルート音)=ファ、左手=ラ+ド+ファだったのが、イパネマでは、足鍵盤=ファの上に、左手=ミ+ラ+レが乗る。そして、メロディーも「ソッミミーレ ソッミッミーミレ」と、ラ・ド・ファは出てこない。さらにバッキングのリズムは、2拍4拍の裏打ちではなく、シンコペーションを刻む。これには困惑し、驚いた。
―― と同時にものすごく気持ちが良かった。しばらくは、その浮遊感あるハーモニーとさざ波のようなリズムの虜となり、先生に「もっと他にもこういうのはないのか」とオネダリをしたのを覚えている…。
そんな別惑星からの使者、ジョビンへの敬愛から生まれた「アントニオの歌」。ジャズ・フュージョン界のトップアーティストを集めた洗練のサウンドと、マイケル・フランクスの囁くような甘い歌声。それだけでも十分に魅力的なのだが、この曲を印象づけたのは、なんといってもサビのメロディー3音だろう。
But sing the Song
ド ソ# シ
(キーは Am)
伝わるだろうか、この妖艶な響き。そして、この「ドソ#シ」は、ストリングスによるカウンターメロディーの一部として、曲中で幾度も繰り返される。
ひねりのないコードでいくと E7 → Am で済むところを、このメロディー3音で Eaug7 → Am add9 を表現しているのだ。特に Am(ラ+ド+ミ)に乗るシの音、いわゆるナインス(9th)の響きが、翳りある雰囲気を醸しだし、切なげでクールなボサノバチューンとしての完成度を高めている。
こうしてボサノバ、AOR のフィーリングを絶妙にブレンドし、歌ものポップスとして耳なじみの良い仕上がりとなった「アントニオの歌」は、世界的なヒットとなり、その後多くのアーティストにカバーされた。そして、ジョビンの楽曲がマイケル・フランクスに大きな衝撃を与えたように、日本の作曲家にも大きな影響を及ぼしたと思われる。
マイナー(短調)のボサノバ調の曲に焦点を絞って、すぐに思い浮かぶのが「あの日にかえりたい」荒井由実(75年)。そして、「どうぞこのまま」丸山圭子(76年)である。なんとこの2曲は「アントニオの歌」以前のリリースだ。日本ボサノバ歌謡の先駆け、恐るべし。
振り返ると、60〜70年代のムード歌謡にも、所々に複雑なコードが見受けられる。だがそれらは、ラテンの中でもカリブ系のルンバやマンボ、チャチャチャから派生したものと思われ、ブラジル発祥のボサノバ流派とは別ものと想定される。何よりリズムがシンコペーションの「さざ波」ではない。そういった意味では、いち早くポップスにボサノバを取り入れたユーミン、丸山圭子は、実に偉大である。
そして、80年代に入ると、あの「ドソ#シ」が歌謡曲のメロディーに現れ、妖艶な響きを放ちはじめる。
テレサ・テン
「つぐない」(作曲:三木たかし / 1984)
♪ 窓に西陽が…
ミドソ#シシーララー
桑田佳祐による『3大ドソ#シ』
「私はピアノ」(1980)
♪ くりかえすのはただ lonely play
ラドレレレレミーレシー ドソ#シーラー
「匂艶THE NIGHT CLUB」(1982)
♪ 俺の Kiss は きっと痛いよ
ミレドーレミソファー レミーミドソ#シーラー
「Long-haired Lady」(1985)
♪ 波音も濡れている Hello Darkness
ドソ#シーラミー ミドソーファシー
ファミーレードー
そもそも、音数の少ないシンプルなメロディーの裏で、複雑かつ繊細なハーモニーがうごめくボサノバの曲。それに、70年代後半からの AOR 人気が後押しをして、「アントニオの歌」につづくように、日本でもボサノバフレーバーの物憂げな歌謡曲が続々と登場していった。音楽に対して「都会的」という新たな評価基準が加わったのもこの頃だろう。
最後に、ボサノバ誕生から60年、地球の裏側に思いを馳せつつ、ボサノバ歌謡創成期の超私的ベストテンを発表(今回はマイナーキーのもの限定)。のちにユーミンの「あの日にかえりたい」をカバーしているマイケル・フランクスに、できることならこれらの曲も歌って欲しいものだ。
第10位 菊池桃子「もう逢えないかもしれない」(1985)
■作編曲:林哲司
第9位 鈴木雄大「レイニーサマー」(1983)
■作編曲:都倉俊一
第8位 早見優「哀愁情句」(1984)
■作曲:筒美京平 / 編曲:船山基紀
第7位 五十嵐浩晃「愛は風まかせ」(1980)
■作曲:五十嵐浩晃 / 編曲:鈴木茂
第6位 研ナオコ「夏をあきらめて」(1982)
■作曲:桑田佳祐 / 編曲:若草恵
第5位 サーカス「Mr.サマータイム」(1978)
■作曲:Michel Fugain / 編曲:前田憲男
第4位 稲垣潤一「ドラマティック・レイン」(1982)
■作曲:筒美京平 / 編曲:船山基紀
第3位 中村雅俊「恋人も濡れる街角」(1982)
■作曲:桑田佳祐 / 編曲:桑田佳祐、八木正生
第2位 桐ヶ谷仁「さらば愛の日々」(1981)
■作曲:桐ヶ谷仁 / 編曲:松原正樹、松任谷正隆
第1位 杉山清貴&オメガトライブ「君のハートはマリンブルー」(1984)
■作編曲:林哲司
2018.09.18
Spotify
Spotify
Information
あなた
























