この日何の日?
坂本龍一のアルバム「スムーチー」発売日(ポエジア 収録)
この時あなたは
0歳
無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます
1995年のコラム
TVアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の斬新さと高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」
始まりは DAICON3!庵野秀明が【新世紀エヴァンゲリオン】を生み出すまでの長ーい物語
ゴールデンウィークに観たいアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」② まさにアニメ文化の分水嶺
【佐橋佳幸の40曲】氷室京介「魂を抱いてくれ」迫力ストリングスと松本隆の描くヒムロック
エヴァンゲリオンのテーマ曲「残酷な天使のテーゼ」どうして女性に支持されるのだろう?
高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」エヴァの主題歌はなぜ国民的ヒットになったのか?
もっとみる≫

連載【佐橋佳幸の40曲】vol.13
ポエジア / 坂本龍一
作曲:坂本龍一
編曲:坂本龍一
山下達郎、大貫妙子、村松邦男らが結成していたポップグループ、シュガー・ベイブ。今さら詳しい説明は不要だろう。1975年にたった1枚の傑作アルバムを残しただけで解散してしまった伝説のバンドだ。そんな彼らの唯一のアルバム『SONGS』のオリジナルマスターによる初CD化が1994年に実現。同年4月から5月にかけて、それを記念するコンサートも開催された。それが山下達郎による『TATSURO YAMASHITA Sings SUGAR BABE』(全4公演)。
ゲストに大貫妙子を迎え、山下達郎がシュガー・ベイブのレパートリーを歌う。今なお語り継がれるこの歴史的コンサートが、佐橋にとって山下達郎バンドのギタリストとしての初ステージとなった。中学時代の佐橋に多大な影響を与え、彼の未来を決める大きなきっかけとなったシュガー・ベイブを再現する舞台に立つ。どこか不思議な巡り合わせを感じる体験でもあった。

このコンサートには『SONGS』プロデューサーだった大瀧詠一をはじめ、シュガー・ベイブと共に70年代を生きた音楽仲間たちも数多く詰めかけた。終演後のバックステージはちょっとした同窓会状態。その中に坂本龍一がいた。ステージ上で奮闘する若き佐橋のプレイに目を止めた坂本が、「山下、あのギタリストを紹介してくれよ」と言い、山下達郎が佐橋を坂本に紹介したというのは有名なエピソードだが…。
「実は、初対面はその数年前だったの。僕が80年代終わりから所属していたTOPは、藤井丈司さんやエンジニアの飯尾芳史さんや… YMO周辺の人たちがたくさんいた事務所。そこで仲良くなったマネージャーとふたりでニューヨークに遊びに行ったことがあってね。その時、ニューヨーク郊外にあった坂本さんと矢野さんのお宅にお邪魔をしているの。すでに矢野さんとは『LOVE LIFE』のレコーディングで知り合っていたけど、教授とは初対面。娘さんの美雨ちゃんがまだ中学生くらいだったのかな。彼女の部屋から渡辺美里の『Lovin' you』が流れてきて、“ちなみにこのギター、僕です” “へぇー!” みたいな(笑)。それで、中野サンプラザで達郎さんから紹介された時に “あの時、お宅にお邪魔したサハシです” となったわけ」
それから約4カ月後の1994年9月、同じ中野サンプラザのステージで佐橋は坂本との初共演を果たした。坂本のワールド・ツアー 『Sweet Revenge』最終公演。このツアーにはギタリストとして高野寛が参加していたのだが、残念なことに最終公演だけ、どうしても高野のスケジュールが合わなかった。そこでツアー最終日、高野の代役を務めてくれるギタリストを探す中、坂本は佐橋に白羽の矢を立てた。
「教授が “あ、あの時の山下のバンドの…” って、僕のことを思い出してくれたらしい。でも、この時リハーサルスタジオに行った記憶がないんだよ。前日の公演を見て、翌日の最終日の昼にコンサート会場でやったリハーサルで初めてバンドと一緒に演奏したんだと思います。自分でいうのも何だけど、これ、けっこうすごいことだったと思うよ(笑)。若かったから、俺、がんばったんだな。それで、教授が気に入ってくれて。今後いろいろ手伝って欲しい、という話になった」

1994年、坂本は自身のレーベル “güt(グート)” を設立し、日本ではフォーライフ・レコードに移籍(海外盤はエレクトラからのリリース)。レーベル第1弾のソロアルバム『スウィート・リヴェンジ』(94年6月)を発表、久々に日本国内でも本格的な活動を再開していた。佐橋は、95年10月にリリースされたソロ作『スムーチー』で坂本作品のレコーディングに初参加。その後gütレーベルからリリースされた数々の作品に深く関わってゆくことになる。
「その前にライヴでも共演したけど。やっぱり『スムーチー』が本当の意味での始まりですね。僕が弾いている曲は教授が中谷(美紀)さんとデュエットした「愛してる、愛してない」とか、最後に入っている「ア・デイ・イン・ザ・パーク」とか…。どの曲も思い出深いけど。なかでも「ポエジア」でのギタープレイは、僕としても、坂本作品としても、ちょっと珍しい雰囲気をかもしだしているんじゃないかな」
「最初に曲を聴いた時、マリア・マルダーの「真夜中のオアシス」っぽいイメージで、エリック・ゲイルにエイモス・ギャレットがちょっと入ったような感じで弾いてみたらいいんじゃないかなと思ったの。それで、そういうふうに教授に提案してみたら “何それ、やってみてやってみてー” と面白がってくれた。たしかこれ、1テイクで決まったんです。教授は “早録り” なんですね。集中してガッと短時間で仕上げる。“いいよいいよ。ちょっと間違えちゃったけど、そのままでいいよいいよ” みたいなこともあった(笑)」

アルバム完成後に行われた全国ツアー『坂本龍一 TOUR '95 [D&L]』、今度は代役ではなく正式なツアーギタリストとして参加した。
「このツアーにはふたつ、大きなコンセプトがあって。ひとつは、当時、教授がクリエイターの原田大三郎さんとすごく懇意にしていた時期で、このツアーも原田さんの映像作品とのコラボレーションだったの。もうひとつのコンセプトは、メンバーほぼ全員の国籍が違うということ。アメリカ、イギリス、デンマーク、ブラジル… 日本人は、僕と森俊彦くんのふたりだけ。ライヴも楽しかったし、世界各国のミュージシャンたちとの珍道中も忘れられない(笑)。地方で古い日本旅館に泊まることになった時に外人チームが大興奮で、大浴場でお風呂の入り方を教えてあげたこととか。ブラジルから来たヤツがホームシックになっちゃって、西麻布のブラジル料理屋さんに連れて行って励ましてあげたこととか」
「ツアーの合間、デイヴィッド・サンボーンの来日公演があって、彼と一緒にやっていたメンバーに誘われて観に行ったこともあった。ちょうど僕のソロアルバム『トラスト・ミー』が出たばかりで、終演後に紹介してもらった時に連絡先と一緒に渡したの。“わーい、サンボーンに渡しちゃったよ” って喜んでいたら、翌朝いきなりウチにサンボーンから電話がかかってきて “聴いたよ。2曲目めっちゃよかった” って(笑)。まさか直電とは。そんなこともあった。懐かしいなぁ」
gütレーベル時代の坂本は、メロディに比重を置いた新しいポップミュージックの定義に情熱を注ぎ試行錯誤していた。それゆえ、日本という独自のマーケットにおけるポップスのあり方に誰よりも精通したミュージシャンである佐橋の存在は重宝された。どんなジャンルの曲でも的確に意図を汲んで弾きこなすうえ、オタクならではのマニアックなアイディアを豊富に持ち合わせる佐橋は、この時期の坂本にとっての “懐刀” とも言えるギタリストだった。
実娘、坂本美雨のデビュー作となった “坂本龍一 featuring Sister M” 名義での「The Other Side of Love」、中谷美紀の「砂の果実」「MIND CIRCUS」、ダウンタウンが振袖に相撲のまわしというニセ芸者に扮した覆面ユニットGEISHA GIRLSの「少年」でサイモン&ガーファンクル風のギターとハーモニーを担当していたのも、実は佐橋だったりする。
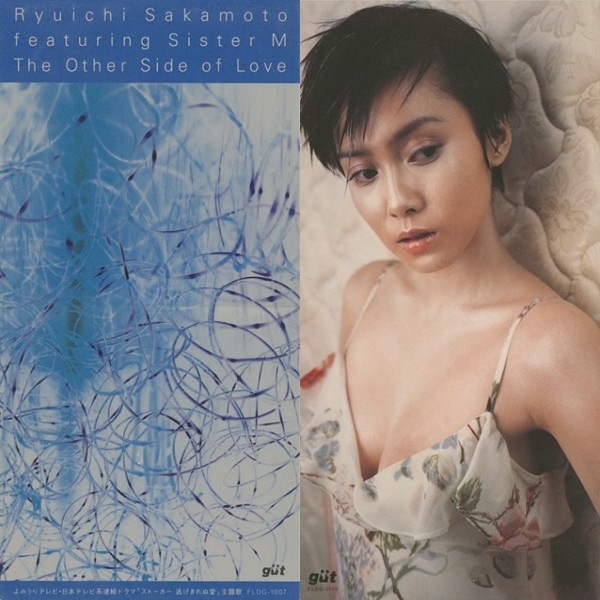
「ライヴもやって、レコーディングでもいろんな作品にかなり濃密に関わらせてもらうことができた。レコーディングの拠点は通称 “駒パラ” 、駒沢にあったフォーライフ・レコードのパラダイス・スタジオというところだったんだけど。ひとつレコーディングが終わっても、翌日には別のプロジェクトが始まるとか。そんなこともあった。だから、僕、楽器を置きっぱなしにしていたくらい常駐してました(笑)。なかでもめちゃめちゃ面白い経験だったと今でも思うのは、ドラマ『ストーカー 逃げきれぬ愛』のサウンドトラック(1997年リリース)。美雨ちゃんのデビュー曲「The Other Side of Love」がオープニング曲になって。で、ドラマのサントラも教授が手がけることになったの」
「ところが、教授がニューヨークと東京を行ったり来たりの忙しい時期だったので、僕ががっつり手伝うことになり、結局、サントラ盤も僕と坂本さんの共同名義でリリースされたんです。ニューヨークにいる教授と東京にいる僕が一度も直接会うことなく、ネットでデータをやりとりしながらレコーディング。ま、今だったら iPhone でもできちゃうような、珍しくもなんともないフツーの作業だよね。でも、当時はまだインターネット黎明期。いちばん早いネット回線でもISDNだったでしょ。もう、前代未聞の大プロジェクトだったわけ」
「坂本さんがマイクロソフトの社長に直談判して、僕には何だかよくわからないようなおそろしい機材の数々をスタジオに運びこませて…(笑)。ニューヨークにいる教授が弾いたモチーフのデータが送られてくる。で、届いたモチーフを “上の句” として、今度は僕が “下の句” を作る… みたいなやりとりを繰り返して曲を仕上げていった。でもね、何度も言うように時は90年代半ばですよ。ワンフレーズをダウンロードするだけで2時間くらいかかるわけ。その間、僕は教授と電話で話したり、メールのやりとりをしたり、あるいは別の曲を録ってたり…。大変だったけど、楽しかったよ。坂本さん世代の先輩たちはみんな、そういう新しいことが大好きだったよね。常にアンテナを張り巡らして、まだ誰もやってないことをやってやろう… みたいな。あの時代、そういう熱気のある現場にいられたのは幸運だった。ものすごく勉強になった」
写真提供:佐橋佳幸

この時期の佐橋が坂本からさまざまなことを吸収していたのと同じように、現在進行中のJ-POP最前線にいながらにして、若いくせに70年代の “日本語のロック” シーンにも精通した佐橋から坂本が得たものも少なくはなかった。
「たしかに、ただ演奏するだけじゃなくて、いろいろ相談されたし。いろんな人を紹介したもん。“こういうのが得意な人、いないかな?” とか、“今、こういうことやるなら、日本では誰に頼むのがいちばんいいの?” みたいなことを、ことあるごとに聞かれたよ。そういえば “佐橋くん以外で、今、キテるなーっていうギタリストいない?” って聞かれたから、オグちゃん(小倉博和)を紹介したんだよ(笑)」
「若手のことだけでなく、教授が70年代に一緒にやっていたような人たちの話もよくした。“あの人はどうしてる? 元気なの?” とかね。“ペダル・スチールを呼ぶなら今でもコマコ(駒沢裕城)がいいの?” って聞かれた時には、そういえばこの人はナイアガラ・レコード時代の達郎さんの「パレード」でピアノを弾いている人だったんだもんなぁとあらためて思い出しましたよ。長いこと海外を拠点にしていたから、日本の音楽シーンに関してはちょっと浦島太郎的な面もあったと思う。ご本人もそれは実感していたみたいで、僕に限らずいろんな人にいろんなことを聞いていた。教授は自分が信頼している人から “今、この人が面白いですよ” って聞くとすぐに起用する。そういう “スピード感” をひとつの個性というか信念としてずっと持っていた人だ… と、よく言われるけど。ある意味、そのブレーン的なひとりとして、あの時期にお手伝いできたのは光栄でした」
たまたま最終公演だけ代役ギタリストを務めることになったツアーのステージから始まった坂本龍一との縁。しかし、この連載をお読みの方々ならば、ちょっとビックリしたはず。そのツアーのタイトルがUGUISSのデビュー曲と同じ “Sweet Revenge” だったということに…。ここにもまた、サハシヒストリーに散りばめられた不思議な縁を感じずにはいられない。
「そうなんだよね。このタイミングでこのコトバが出てくるなんて。何だかね、偶然にしては出来すぎてる。あの時は、さすがに教授にいきなり “俺がやってたUGUISSってバンドがあるんですけどぉ…” なんて説明してもしょうがないから何も言わなかったけどさ(笑)。内心では、自分でもビックリしてたの。なんなんだろう、これは… と」
次回【山下久美子「TOKYO FANTASIA」稀代のヒットメーカー筒美京平との縁】につづく
2024.02.10
ポエジア / 坂本龍一
作曲:坂本龍一
編曲:坂本龍一
山下達郎バンドのギタリストとしての初ステージはシュガー・ベイブの再演
山下達郎、大貫妙子、村松邦男らが結成していたポップグループ、シュガー・ベイブ。今さら詳しい説明は不要だろう。1975年にたった1枚の傑作アルバムを残しただけで解散してしまった伝説のバンドだ。そんな彼らの唯一のアルバム『SONGS』のオリジナルマスターによる初CD化が1994年に実現。同年4月から5月にかけて、それを記念するコンサートも開催された。それが山下達郎による『TATSURO YAMASHITA Sings SUGAR BABE』(全4公演)。
ゲストに大貫妙子を迎え、山下達郎がシュガー・ベイブのレパートリーを歌う。今なお語り継がれるこの歴史的コンサートが、佐橋にとって山下達郎バンドのギタリストとしての初ステージとなった。中学時代の佐橋に多大な影響を与え、彼の未来を決める大きなきっかけとなったシュガー・ベイブを再現する舞台に立つ。どこか不思議な巡り合わせを感じる体験でもあった。
山下、あのギタリストを紹介してくれよ

このコンサートには『SONGS』プロデューサーだった大瀧詠一をはじめ、シュガー・ベイブと共に70年代を生きた音楽仲間たちも数多く詰めかけた。終演後のバックステージはちょっとした同窓会状態。その中に坂本龍一がいた。ステージ上で奮闘する若き佐橋のプレイに目を止めた坂本が、「山下、あのギタリストを紹介してくれよ」と言い、山下達郎が佐橋を坂本に紹介したというのは有名なエピソードだが…。
「実は、初対面はその数年前だったの。僕が80年代終わりから所属していたTOPは、藤井丈司さんやエンジニアの飯尾芳史さんや… YMO周辺の人たちがたくさんいた事務所。そこで仲良くなったマネージャーとふたりでニューヨークに遊びに行ったことがあってね。その時、ニューヨーク郊外にあった坂本さんと矢野さんのお宅にお邪魔をしているの。すでに矢野さんとは『LOVE LIFE』のレコーディングで知り合っていたけど、教授とは初対面。娘さんの美雨ちゃんがまだ中学生くらいだったのかな。彼女の部屋から渡辺美里の『Lovin' you』が流れてきて、“ちなみにこのギター、僕です” “へぇー!” みたいな(笑)。それで、中野サンプラザで達郎さんから紹介された時に “あの時、お宅にお邪魔したサハシです” となったわけ」
それから約4カ月後の1994年9月、同じ中野サンプラザのステージで佐橋は坂本との初共演を果たした。坂本のワールド・ツアー 『Sweet Revenge』最終公演。このツアーにはギタリストとして高野寛が参加していたのだが、残念なことに最終公演だけ、どうしても高野のスケジュールが合わなかった。そこでツアー最終日、高野の代役を務めてくれるギタリストを探す中、坂本は佐橋に白羽の矢を立てた。
「教授が “あ、あの時の山下のバンドの…” って、僕のことを思い出してくれたらしい。でも、この時リハーサルスタジオに行った記憶がないんだよ。前日の公演を見て、翌日の最終日の昼にコンサート会場でやったリハーサルで初めてバンドと一緒に演奏したんだと思います。自分でいうのも何だけど、これ、けっこうすごいことだったと思うよ(笑)。若かったから、俺、がんばったんだな。それで、教授が気に入ってくれて。今後いろいろ手伝って欲しい、という話になった」
ちょっと珍しい雰囲気をかもしだしている「ポエジア」でのギタープレイ

1994年、坂本は自身のレーベル “güt(グート)” を設立し、日本ではフォーライフ・レコードに移籍(海外盤はエレクトラからのリリース)。レーベル第1弾のソロアルバム『スウィート・リヴェンジ』(94年6月)を発表、久々に日本国内でも本格的な活動を再開していた。佐橋は、95年10月にリリースされたソロ作『スムーチー』で坂本作品のレコーディングに初参加。その後gütレーベルからリリースされた数々の作品に深く関わってゆくことになる。
「その前にライヴでも共演したけど。やっぱり『スムーチー』が本当の意味での始まりですね。僕が弾いている曲は教授が中谷(美紀)さんとデュエットした「愛してる、愛してない」とか、最後に入っている「ア・デイ・イン・ザ・パーク」とか…。どの曲も思い出深いけど。なかでも「ポエジア」でのギタープレイは、僕としても、坂本作品としても、ちょっと珍しい雰囲気をかもしだしているんじゃないかな」
「最初に曲を聴いた時、マリア・マルダーの「真夜中のオアシス」っぽいイメージで、エリック・ゲイルにエイモス・ギャレットがちょっと入ったような感じで弾いてみたらいいんじゃないかなと思ったの。それで、そういうふうに教授に提案してみたら “何それ、やってみてやってみてー” と面白がってくれた。たしかこれ、1テイクで決まったんです。教授は “早録り” なんですね。集中してガッと短時間で仕上げる。“いいよいいよ。ちょっと間違えちゃったけど、そのままでいいよいいよ” みたいなこともあった(笑)」

坂本龍一のツアーギタリストとして参加
アルバム完成後に行われた全国ツアー『坂本龍一 TOUR '95 [D&L]』、今度は代役ではなく正式なツアーギタリストとして参加した。
「このツアーにはふたつ、大きなコンセプトがあって。ひとつは、当時、教授がクリエイターの原田大三郎さんとすごく懇意にしていた時期で、このツアーも原田さんの映像作品とのコラボレーションだったの。もうひとつのコンセプトは、メンバーほぼ全員の国籍が違うということ。アメリカ、イギリス、デンマーク、ブラジル… 日本人は、僕と森俊彦くんのふたりだけ。ライヴも楽しかったし、世界各国のミュージシャンたちとの珍道中も忘れられない(笑)。地方で古い日本旅館に泊まることになった時に外人チームが大興奮で、大浴場でお風呂の入り方を教えてあげたこととか。ブラジルから来たヤツがホームシックになっちゃって、西麻布のブラジル料理屋さんに連れて行って励ましてあげたこととか」
「ツアーの合間、デイヴィッド・サンボーンの来日公演があって、彼と一緒にやっていたメンバーに誘われて観に行ったこともあった。ちょうど僕のソロアルバム『トラスト・ミー』が出たばかりで、終演後に紹介してもらった時に連絡先と一緒に渡したの。“わーい、サンボーンに渡しちゃったよ” って喜んでいたら、翌朝いきなりウチにサンボーンから電話がかかってきて “聴いたよ。2曲目めっちゃよかった” って(笑)。まさか直電とは。そんなこともあった。懐かしいなぁ」
坂本にとっての “懐刀” とも言えるギタリスト
gütレーベル時代の坂本は、メロディに比重を置いた新しいポップミュージックの定義に情熱を注ぎ試行錯誤していた。それゆえ、日本という独自のマーケットにおけるポップスのあり方に誰よりも精通したミュージシャンである佐橋の存在は重宝された。どんなジャンルの曲でも的確に意図を汲んで弾きこなすうえ、オタクならではのマニアックなアイディアを豊富に持ち合わせる佐橋は、この時期の坂本にとっての “懐刀” とも言えるギタリストだった。
実娘、坂本美雨のデビュー作となった “坂本龍一 featuring Sister M” 名義での「The Other Side of Love」、中谷美紀の「砂の果実」「MIND CIRCUS」、ダウンタウンが振袖に相撲のまわしというニセ芸者に扮した覆面ユニットGEISHA GIRLSの「少年」でサイモン&ガーファンクル風のギターとハーモニーを担当していたのも、実は佐橋だったりする。
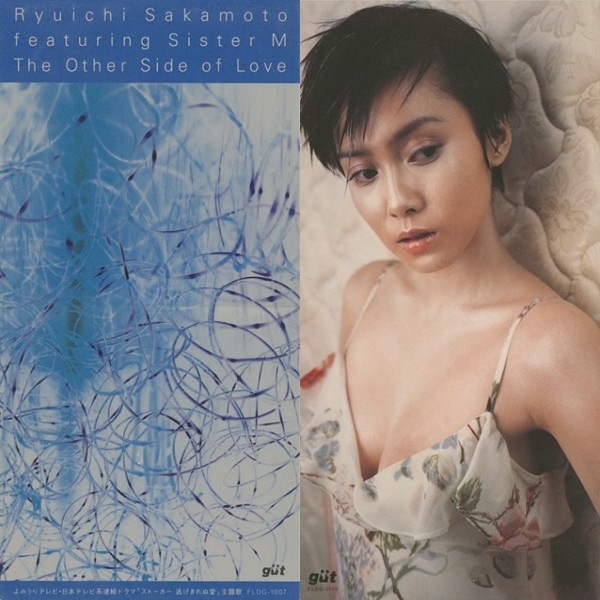
「ライヴもやって、レコーディングでもいろんな作品にかなり濃密に関わらせてもらうことができた。レコーディングの拠点は通称 “駒パラ” 、駒沢にあったフォーライフ・レコードのパラダイス・スタジオというところだったんだけど。ひとつレコーディングが終わっても、翌日には別のプロジェクトが始まるとか。そんなこともあった。だから、僕、楽器を置きっぱなしにしていたくらい常駐してました(笑)。なかでもめちゃめちゃ面白い経験だったと今でも思うのは、ドラマ『ストーカー 逃げきれぬ愛』のサウンドトラック(1997年リリース)。美雨ちゃんのデビュー曲「The Other Side of Love」がオープニング曲になって。で、ドラマのサントラも教授が手がけることになったの」
「ところが、教授がニューヨークと東京を行ったり来たりの忙しい時期だったので、僕ががっつり手伝うことになり、結局、サントラ盤も僕と坂本さんの共同名義でリリースされたんです。ニューヨークにいる教授と東京にいる僕が一度も直接会うことなく、ネットでデータをやりとりしながらレコーディング。ま、今だったら iPhone でもできちゃうような、珍しくもなんともないフツーの作業だよね。でも、当時はまだインターネット黎明期。いちばん早いネット回線でもISDNだったでしょ。もう、前代未聞の大プロジェクトだったわけ」
「坂本さんがマイクロソフトの社長に直談判して、僕には何だかよくわからないようなおそろしい機材の数々をスタジオに運びこませて…(笑)。ニューヨークにいる教授が弾いたモチーフのデータが送られてくる。で、届いたモチーフを “上の句” として、今度は僕が “下の句” を作る… みたいなやりとりを繰り返して曲を仕上げていった。でもね、何度も言うように時は90年代半ばですよ。ワンフレーズをダウンロードするだけで2時間くらいかかるわけ。その間、僕は教授と電話で話したり、メールのやりとりをしたり、あるいは別の曲を録ってたり…。大変だったけど、楽しかったよ。坂本さん世代の先輩たちはみんな、そういう新しいことが大好きだったよね。常にアンテナを張り巡らして、まだ誰もやってないことをやってやろう… みたいな。あの時代、そういう熱気のある現場にいられたのは幸運だった。ものすごく勉強になった」
スピード感”をひとつの個性というか信念としてずっと持っていた人
写真提供:佐橋佳幸

この時期の佐橋が坂本からさまざまなことを吸収していたのと同じように、現在進行中のJ-POP最前線にいながらにして、若いくせに70年代の “日本語のロック” シーンにも精通した佐橋から坂本が得たものも少なくはなかった。
「たしかに、ただ演奏するだけじゃなくて、いろいろ相談されたし。いろんな人を紹介したもん。“こういうのが得意な人、いないかな?” とか、“今、こういうことやるなら、日本では誰に頼むのがいちばんいいの?” みたいなことを、ことあるごとに聞かれたよ。そういえば “佐橋くん以外で、今、キテるなーっていうギタリストいない?” って聞かれたから、オグちゃん(小倉博和)を紹介したんだよ(笑)」
「若手のことだけでなく、教授が70年代に一緒にやっていたような人たちの話もよくした。“あの人はどうしてる? 元気なの?” とかね。“ペダル・スチールを呼ぶなら今でもコマコ(駒沢裕城)がいいの?” って聞かれた時には、そういえばこの人はナイアガラ・レコード時代の達郎さんの「パレード」でピアノを弾いている人だったんだもんなぁとあらためて思い出しましたよ。長いこと海外を拠点にしていたから、日本の音楽シーンに関してはちょっと浦島太郎的な面もあったと思う。ご本人もそれは実感していたみたいで、僕に限らずいろんな人にいろんなことを聞いていた。教授は自分が信頼している人から “今、この人が面白いですよ” って聞くとすぐに起用する。そういう “スピード感” をひとつの個性というか信念としてずっと持っていた人だ… と、よく言われるけど。ある意味、そのブレーン的なひとりとして、あの時期にお手伝いできたのは光栄でした」
たまたま最終公演だけ代役ギタリストを務めることになったツアーのステージから始まった坂本龍一との縁。しかし、この連載をお読みの方々ならば、ちょっとビックリしたはず。そのツアーのタイトルがUGUISSのデビュー曲と同じ “Sweet Revenge” だったということに…。ここにもまた、サハシヒストリーに散りばめられた不思議な縁を感じずにはいられない。
「そうなんだよね。このタイミングでこのコトバが出てくるなんて。何だかね、偶然にしては出来すぎてる。あの時は、さすがに教授にいきなり “俺がやってたUGUISSってバンドがあるんですけどぉ…” なんて説明してもしょうがないから何も言わなかったけどさ(笑)。内心では、自分でもビックリしてたの。なんなんだろう、これは… と」
次回【山下久美子「TOKYO FANTASIA」稀代のヒットメーカー筒美京平との縁】につづく
アナタにおすすめのコラム
2024.02.10
Songlink
Information
あなた
























