この日何の日?
フジテレビ系ドラマ「踊る大捜査線」第10話「凶弾・雨に消えた刑事の涙」放送日
この時あなたは
0歳
無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます
1997年のコラム
織田裕二主演ドラマ「踊る大捜査線」もしリメイクされるならどんなメンツで観たい?
千秋の涙から誕生したポケットビスケッツ!勇敢なメッセージソング「Red Angel」
今この瞬間の勇気!JUDY AND MARY「くじら12号」新しい年にふさわしい90年代の名曲
【平成の春うた】松たか子「明日、春が来たら」わくわく新生活!希望に満ちた季節到来
【佐橋佳幸の40曲】川本真琴「1/2」天才マニピュレーター・石川鉄男との絶大なる信頼関係
広末涼子「MajiでKoiする5秒前」竹内まりやが勝負に挑んだ100%のアイドルソング!
もっとみる≫

連載【新・黄金の6年間 1993-1998】vol.24
その刑事ドラマには、いくつかの “禁じ手” があった。
▶︎ 刑事があだ名で呼び合わない
▶︎ たった7人で捜査会議をしない
▶︎ 音楽に乗せて聞き込みをしない
▶︎ 犯人に感情移入しない
▶︎ 新人刑事は殉職しない
―― etc
要するに――『太陽にほえろ!』(日本テレビ系)にしないということだった。「全く新しい刑事ドラマを作りたい」―― それがフジテレビの亀山千広プロデューサー(当時)が掲げたビジョンだった。当初から “警察署の組織もの” という大枠のアイデアはあったという。キャストは主演の織田裕二サンとヒロインの深津絵里サンの2人のみが決まっていた。
企画にあたって最初に呼ばれたのが、フジテレビの編成部(当時)の石原隆サンだった。亀山サンは織田サンと仕事をするのは初めてなので、かつて『振り返れば奴がいる』や『お金がない!』で織田サンと組んだ石原サンに助言を求めたのだ。「演出は、主演俳優がやりやすい人がいいでしょう」―― 早速、事務所を通じて織田サンの意向を尋ねると、返ってきた答えが『お金がない!』のサードディレクター、本広克行サンがいいと。脚本は、「群像劇なら『コーチ』を書いた君塚良一サンが適任でしょう」と、こちらも石原サンの推薦だった。
かくして、亀山・石原・本広・君塚の4氏で企画会議が持たれ、冒頭の「禁じ手」が共有されたのである。そして企画を練るうちに君塚サンが、映画『仁義なき戦い』シリーズ3作目の『仁義なき戦い 代理戦争』の世界観を思いつく。「命を賭けて、意地を張って、プライドで話し合ってる人たちなんだけど、傍から見たら笑える」―― ここから、“登場人物たちはみんな真剣なんだけど、傍から見ればコメディ” というドラマの方向性が固まった。
タイトルは皆で出し合っているうち、石原サンが次の会議に出ないといけないと、退室間際にホワイトボードに書き残した案が採用された。ちなみに、彼は映画『私をスキーに連れてって』(監督:馬場康夫)のタイトルの考案者でもある。
そうして―― フジテレビ系の新しい連続ドラマが決まった。放映クールは1997年1月から3月。舞台は、同年3月にフジテレビが本社を移転する港区お台場。枠は火曜夜9時。タイトルは――『踊る大捜査線』である。今日、3月11日は今から27年前の1997年に、同ドラマの最高傑作回と評される第10話「凶弾・雨に消えた刑事の涙」がオンエアされた日にあたる――。
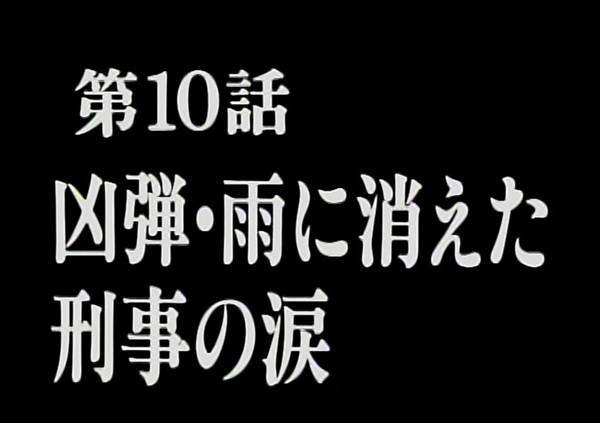
日本の刑事ドラマの扉を開けたのは、TBS系で1961年から9年間に渡って放映された『七人の刑事』だった。同ドラマで描かれた犯人は社会的な背景を持ち、現代における負の部分に警鐘を鳴らすドラマでもあった。“悪いのは俺じゃない。社会だ!” というアレだ。
それを変えたのが、日本テレビ系で1972年から15年間に渡って放映された『太陽にほえろ!』だった。同ドラマは犯人と刑事が織りなす人間ドラマにフォーカスして、それが刑事ドラマの新たなフォーマットになった。刑事たちがあだ名で呼び合ったり、新人刑事が殉職するのも、同ドラマが起点である。
その流れを『踊る大捜査線』はまた変えた。警視庁の本庁の下に所轄署―― いわゆる “ショカツ” がある。捜査会議は本庁がショカツに乗り込んできて、彼らの主導のもと行われる。ショカツに捜査権はなく、弁当やコピー機を手配したり、運転手や検問などの周辺業務を担う。ショカツに属する一兵卒の主人公が、どう抗いても越えられない壁がある。そんな “階級社会” の悲哀が、『踊る』以降、刑事ドラマの新たなリアリティになった。
映画『愛と青春の旅だち』には終盤、海軍の士官候補生たちが卒業式を終えて “士官” となった瞬間、それまで彼らをしごいてきた鬼軍曹との階級が逆転し、鬼軍曹が彼らに “サー” をつけて敬礼するシーンがある。個人的には、リチャード・ギアが製紙工場で働く恋人を迎えにいくラストシーンより、こっちの方がグッと来るが、軍隊も警察組織も厳格な階級社会ゆえに “カセ” が生じる。『踊る』がそこに、ドラマツルギー(物語の方法論)を見出したのは賢明だった。
そして、もう1つ――『踊る』が発明した警察組織の見せ方に、“サラリーマン的手法” もあった。誇張はあるものの、警察関係者への取材過程で仕入れたネタがベースになっており、半分くらいは本当とのこと。こちらはコメディに仕立てやすく、もともと欽ちゃん(萩本欽一)お抱えの構成作家集団 “パジャマ党” 出身の君塚サンの得意分野でもある。これは、第1話「サラリーマン刑事と最初の難事件」で厚めに描かれている。
例えば、警視庁の本庁のことを和久さん(いかりや長介)が「本店」と呼んだり、青島(織田裕二)がパトカーで現場に急行しようとしたら、警務課で貸出書の記入と上司のハンコを求められたり、袴田課長(小野武彦)が勤務中に署長の接待ゴルフに出かけていたり、魚住係長(佐戸井けん太)が二言目には健康診断を受けるよう署員に呼び掛けたり――。
中でも珠玉は、神田署長(北村総一朗)、秋山副署長(斉藤暁)、袴田課長らスリーアミーゴスが真剣に語り合う「戒名」(捜査本部前に掲げる「××殺人事件捜査本部」と書かれたアレ)を決めるシーンだ。このシーンは第1話の最大の見せ場と言っていい。
袴田「港区会社員殺人事件特別捜査本部でどうでしょう」
秋山「会社員? 会社役員でしょ」
袴田「なら、港区会社役員殺人事件…」
秋山「首しめられて殺されたって?」
袴田「なら、港区台場会社役員絞殺事件…」
神田「インパクトないね」
袴田「なら、港区台場会社役員絞殺凶悪殺人事件…」
神田「あの会社からレインボーブリッジ近いよね」
袴田「なら、港区台場レインボーブリッジ付近会社役員絞殺凶悪殺人事件…」
―― とまぁ、3人は終始、真剣に演じているゆえに面白い。実はこのシーン、オンエアで見られるやりとりで君塚サンが脚本に書いたのは半分だけ。あとの半分は現場のアドリブだったとか。ここでスリーアミーゴスが覚醒したことで、同ドラマは何を面白がらせるかの方向性が定まったと言っていい。
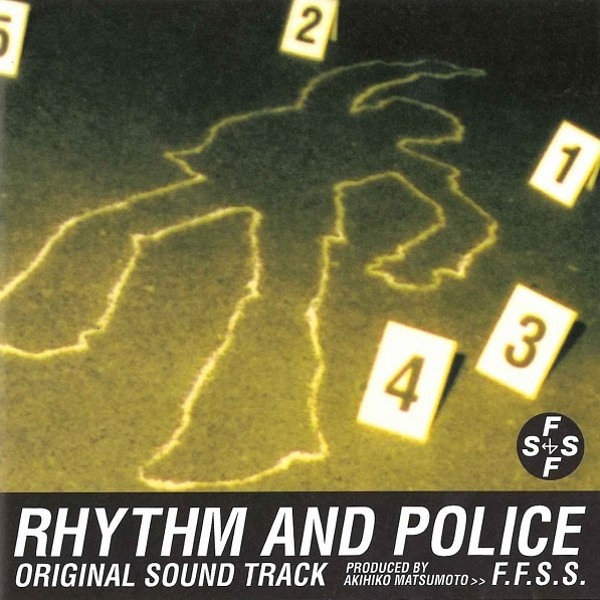
『踊る』の魅力は、映像と音楽にもあった。例えば、オープニングのタイトルバック。空撮好きの本広監督らしく、レインボーブリッジを俯瞰で大胆に煽ったり、主要キャストをマグショット(アメリカの警察が逮捕直後に容疑者を記録する写真)風にインサートで紹介したり、サブタイトルを『ルパン三世』風に出したり――。
BGMで本広監督がどうしても『エヴァンゲリオン』に寄せたくて、庵野秀明監督に直接電話をして、そのまま楽曲を使わせてもらったこともあった。もっとも、『エヴァ』のやつも映画『007 ロシアより愛をこめて』からのオマージュで、これぞ美しきオマージュの連鎖(褒めてます)。エンタメにおけるクリエイティブとは、優れた過去作品をどれだけ知っているかと同義語である。
その意味では、松本晃彦サンが手掛けたメインテーマ曲「Rhythm And Police」もメキシコ音楽の「El cascabel」からのインスパイアで、オマージュ元の意外性と、そのアップデートのクオリティの高さに感心する。エンタメにおけるクリエイティブとは、0から1を生み出すものではない。1を2や3にアップデートする作業である。
そして、主題歌「Love Somebody」(織田裕二 with マキシ・プリースト)が、あの伝説の第10話「凶弾・雨に消えた刑事の涙」のクライマックスシーンに使用され、松本サンのアレンジで “神曲” となったのも忘れられない。同シーンが、『踊る』のテレビシリーズ屈指の名シーンになったのに、かの曲が果たした役割は小さくない。

そう―― 極端なことを言えば、『踊る』のテレビシリーズは、あの第10話のクライマックスを描くために存在したと言っても過言じゃない。第1話で、刑事ドラマの理想の刑事像に憧れ、カタチから入ろうと、アメリカ軍のM-51パーカー(通称:モッズコート)を着込んで、やる気に燃えて湾岸署に赴任した織田裕二演じる青島俊作。しかし――
「殺しは本店の仕切り。ショカツは本店から通達が出るまで待機」―― そんな同僚・すみれ(深津絵里)の言葉に、青島は現実を知る。彼に与えられた仕事は、本店の室井管理官(柳葉敏郎)の運転手だったり、職質でひっかかった男(近藤芳正)の取り調べを担当させられたりと、捜査と関係のない仕事ばかり。ドラマの終盤、犯人が自首したことを知らされ、何も自分が捜査に加われなかったことに落ち込む青島。この時、彼にかける和久さんの言葉がいい。
「お前は運転手をやった。俺は聞き込みの道案内をした。それも刑事の仕事だ」
表情が晴れない青島に、和久さんが続ける。
「犯人に手錠をかけるのは上の者がやればいい。俺たちは犯人を追う兵隊なんだ。それでいい」
この後、自首した犯人が、あの職質で引っかかった男と知り、青島が驚く。この辺り、古今東西のドラマのセオリー “Wストーリー” である。即ち、大きな話(本店が扱う大きな事件)と小さな話(ショカツが扱う小さな事件)が並行して進み、両者は一見、関係がないように見えるが、物語が進むにつれ接近して、交わる。そして小さな事件のほうに、大きな事件を解く重要な鍵がある。『踊る』シリーズは基本、このフォーマットで作られていると言っていい。
そして―― 伝説の第10話である。真下(ユースケ・サンタマリア)が、雪乃(水野美紀)の目の前で撃たれ、救急搬送される。それを知らされた湾岸署の署員たちはいつものお気楽さが消え、空気が一変する。仲間が撃たれたのだ。緊急配備にあたり、拳銃携帯命令が発令される。保管庫の前に整列し、自身のプレートを置いて、銃を手に取る署員たち。ここの描写がやたらカッコいい。君塚サン曰く「現実にあんなシーンは存在しないが、普段は銃を持たない彼らが銃を持つことの重要性を描くのに必要なシーン」と。これを “あたかもリアリティ” と言うらしい。
で、クライマックスだ。雨の中、湾岸署の署員たちは、懸命に検問にあたる。本当は、撃たれた仲間のために犯人を捜査したいのかもしれないが、ショカツにできる仕事は、検問なのだ。だが、それも犯人を検挙するための大事な仕事。ここに至り、視聴者も先の和久さんの言葉を思い出す。「犯人に手錠をかけるのは上の者がやればいい。俺たちは犯人を追う兵隊なんだ。それでいい」――。
このシーンは泣ける。バックにかかるのは、先にも書いたように、主題歌をアレンジした「Love Somebody(Jesus Version)」。この3ヶ月間、『踊る大捜査線』という物語が伝えたかったものが、映像と音楽だけでお茶の間に語られる。これぞ、ドラマの力である。
ちなみに、この第10話の演出を担当したのは、本広監督ではなく、セカンドの澤田鎌作サン。本店とショカツじゃないが、セカンドディレクターが大きな仕事をするところも、実に『踊る』っぽい。
そして、真下警部は殉職しない。
2024.03.11
ドラマの方向性は、“登場人物たちはみんな真剣なんだけど、傍から見ればコメディ”
その刑事ドラマには、いくつかの “禁じ手” があった。
▶︎ 刑事があだ名で呼び合わない
▶︎ たった7人で捜査会議をしない
▶︎ 音楽に乗せて聞き込みをしない
▶︎ 犯人に感情移入しない
▶︎ 新人刑事は殉職しない
―― etc
要するに――『太陽にほえろ!』(日本テレビ系)にしないということだった。「全く新しい刑事ドラマを作りたい」―― それがフジテレビの亀山千広プロデューサー(当時)が掲げたビジョンだった。当初から “警察署の組織もの” という大枠のアイデアはあったという。キャストは主演の織田裕二サンとヒロインの深津絵里サンの2人のみが決まっていた。
企画にあたって最初に呼ばれたのが、フジテレビの編成部(当時)の石原隆サンだった。亀山サンは織田サンと仕事をするのは初めてなので、かつて『振り返れば奴がいる』や『お金がない!』で織田サンと組んだ石原サンに助言を求めたのだ。「演出は、主演俳優がやりやすい人がいいでしょう」―― 早速、事務所を通じて織田サンの意向を尋ねると、返ってきた答えが『お金がない!』のサードディレクター、本広克行サンがいいと。脚本は、「群像劇なら『コーチ』を書いた君塚良一サンが適任でしょう」と、こちらも石原サンの推薦だった。
かくして、亀山・石原・本広・君塚の4氏で企画会議が持たれ、冒頭の「禁じ手」が共有されたのである。そして企画を練るうちに君塚サンが、映画『仁義なき戦い』シリーズ3作目の『仁義なき戦い 代理戦争』の世界観を思いつく。「命を賭けて、意地を張って、プライドで話し合ってる人たちなんだけど、傍から見たら笑える」―― ここから、“登場人物たちはみんな真剣なんだけど、傍から見ればコメディ” というドラマの方向性が固まった。
タイトルは皆で出し合っているうち、石原サンが次の会議に出ないといけないと、退室間際にホワイトボードに書き残した案が採用された。ちなみに、彼は映画『私をスキーに連れてって』(監督:馬場康夫)のタイトルの考案者でもある。
刑事ドラマの流れを大きく変えた「踊る大捜査線」
そうして―― フジテレビ系の新しい連続ドラマが決まった。放映クールは1997年1月から3月。舞台は、同年3月にフジテレビが本社を移転する港区お台場。枠は火曜夜9時。タイトルは――『踊る大捜査線』である。今日、3月11日は今から27年前の1997年に、同ドラマの最高傑作回と評される第10話「凶弾・雨に消えた刑事の涙」がオンエアされた日にあたる――。
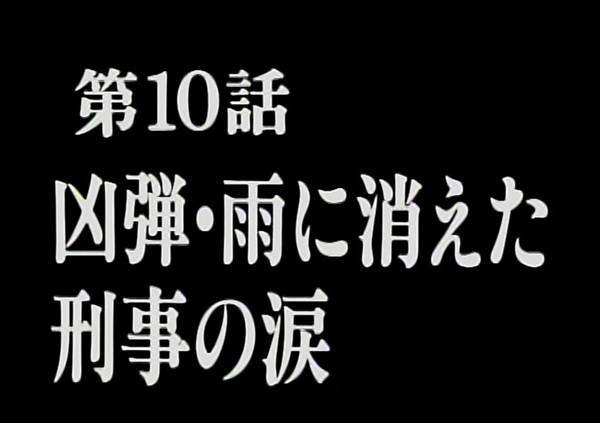
日本の刑事ドラマの扉を開けたのは、TBS系で1961年から9年間に渡って放映された『七人の刑事』だった。同ドラマで描かれた犯人は社会的な背景を持ち、現代における負の部分に警鐘を鳴らすドラマでもあった。“悪いのは俺じゃない。社会だ!” というアレだ。
それを変えたのが、日本テレビ系で1972年から15年間に渡って放映された『太陽にほえろ!』だった。同ドラマは犯人と刑事が織りなす人間ドラマにフォーカスして、それが刑事ドラマの新たなフォーマットになった。刑事たちがあだ名で呼び合ったり、新人刑事が殉職するのも、同ドラマが起点である。
その流れを『踊る大捜査線』はまた変えた。警視庁の本庁の下に所轄署―― いわゆる “ショカツ” がある。捜査会議は本庁がショカツに乗り込んできて、彼らの主導のもと行われる。ショカツに捜査権はなく、弁当やコピー機を手配したり、運転手や検問などの周辺業務を担う。ショカツに属する一兵卒の主人公が、どう抗いても越えられない壁がある。そんな “階級社会” の悲哀が、『踊る』以降、刑事ドラマの新たなリアリティになった。
映画『愛と青春の旅だち』には終盤、海軍の士官候補生たちが卒業式を終えて “士官” となった瞬間、それまで彼らをしごいてきた鬼軍曹との階級が逆転し、鬼軍曹が彼らに “サー” をつけて敬礼するシーンがある。個人的には、リチャード・ギアが製紙工場で働く恋人を迎えにいくラストシーンより、こっちの方がグッと来るが、軍隊も警察組織も厳格な階級社会ゆえに “カセ” が生じる。『踊る』がそこに、ドラマツルギー(物語の方法論)を見出したのは賢明だった。
スリーアミーゴスが真剣に語り合う第1話最大の見せ場
そして、もう1つ――『踊る』が発明した警察組織の見せ方に、“サラリーマン的手法” もあった。誇張はあるものの、警察関係者への取材過程で仕入れたネタがベースになっており、半分くらいは本当とのこと。こちらはコメディに仕立てやすく、もともと欽ちゃん(萩本欽一)お抱えの構成作家集団 “パジャマ党” 出身の君塚サンの得意分野でもある。これは、第1話「サラリーマン刑事と最初の難事件」で厚めに描かれている。
例えば、警視庁の本庁のことを和久さん(いかりや長介)が「本店」と呼んだり、青島(織田裕二)がパトカーで現場に急行しようとしたら、警務課で貸出書の記入と上司のハンコを求められたり、袴田課長(小野武彦)が勤務中に署長の接待ゴルフに出かけていたり、魚住係長(佐戸井けん太)が二言目には健康診断を受けるよう署員に呼び掛けたり――。
中でも珠玉は、神田署長(北村総一朗)、秋山副署長(斉藤暁)、袴田課長らスリーアミーゴスが真剣に語り合う「戒名」(捜査本部前に掲げる「××殺人事件捜査本部」と書かれたアレ)を決めるシーンだ。このシーンは第1話の最大の見せ場と言っていい。
袴田「港区会社員殺人事件特別捜査本部でどうでしょう」
秋山「会社員? 会社役員でしょ」
袴田「なら、港区会社役員殺人事件…」
秋山「首しめられて殺されたって?」
袴田「なら、港区台場会社役員絞殺事件…」
神田「インパクトないね」
袴田「なら、港区台場会社役員絞殺凶悪殺人事件…」
神田「あの会社からレインボーブリッジ近いよね」
袴田「なら、港区台場レインボーブリッジ付近会社役員絞殺凶悪殺人事件…」
―― とまぁ、3人は終始、真剣に演じているゆえに面白い。実はこのシーン、オンエアで見られるやりとりで君塚サンが脚本に書いたのは半分だけ。あとの半分は現場のアドリブだったとか。ここでスリーアミーゴスが覚醒したことで、同ドラマは何を面白がらせるかの方向性が定まったと言っていい。
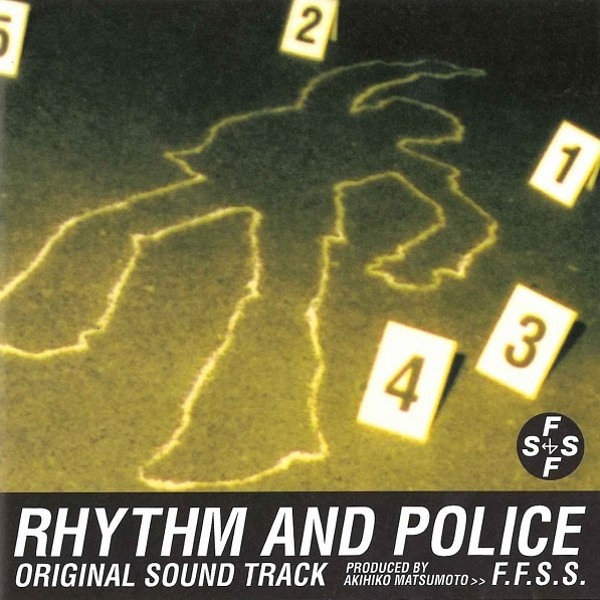
映像と音楽は美しきオマージュの連鎖
『踊る』の魅力は、映像と音楽にもあった。例えば、オープニングのタイトルバック。空撮好きの本広監督らしく、レインボーブリッジを俯瞰で大胆に煽ったり、主要キャストをマグショット(アメリカの警察が逮捕直後に容疑者を記録する写真)風にインサートで紹介したり、サブタイトルを『ルパン三世』風に出したり――。
BGMで本広監督がどうしても『エヴァンゲリオン』に寄せたくて、庵野秀明監督に直接電話をして、そのまま楽曲を使わせてもらったこともあった。もっとも、『エヴァ』のやつも映画『007 ロシアより愛をこめて』からのオマージュで、これぞ美しきオマージュの連鎖(褒めてます)。エンタメにおけるクリエイティブとは、優れた過去作品をどれだけ知っているかと同義語である。
その意味では、松本晃彦サンが手掛けたメインテーマ曲「Rhythm And Police」もメキシコ音楽の「El cascabel」からのインスパイアで、オマージュ元の意外性と、そのアップデートのクオリティの高さに感心する。エンタメにおけるクリエイティブとは、0から1を生み出すものではない。1を2や3にアップデートする作業である。
そして、主題歌「Love Somebody」(織田裕二 with マキシ・プリースト)が、あの伝説の第10話「凶弾・雨に消えた刑事の涙」のクライマックスシーンに使用され、松本サンのアレンジで “神曲” となったのも忘れられない。同シーンが、『踊る』のテレビシリーズ屈指の名シーンになったのに、かの曲が果たした役割は小さくない。

小さな事件のほうに、大きな事件を解く重要な鍵がある
そう―― 極端なことを言えば、『踊る』のテレビシリーズは、あの第10話のクライマックスを描くために存在したと言っても過言じゃない。第1話で、刑事ドラマの理想の刑事像に憧れ、カタチから入ろうと、アメリカ軍のM-51パーカー(通称:モッズコート)を着込んで、やる気に燃えて湾岸署に赴任した織田裕二演じる青島俊作。しかし――
「殺しは本店の仕切り。ショカツは本店から通達が出るまで待機」―― そんな同僚・すみれ(深津絵里)の言葉に、青島は現実を知る。彼に与えられた仕事は、本店の室井管理官(柳葉敏郎)の運転手だったり、職質でひっかかった男(近藤芳正)の取り調べを担当させられたりと、捜査と関係のない仕事ばかり。ドラマの終盤、犯人が自首したことを知らされ、何も自分が捜査に加われなかったことに落ち込む青島。この時、彼にかける和久さんの言葉がいい。
「お前は運転手をやった。俺は聞き込みの道案内をした。それも刑事の仕事だ」
表情が晴れない青島に、和久さんが続ける。
「犯人に手錠をかけるのは上の者がやればいい。俺たちは犯人を追う兵隊なんだ。それでいい」
この後、自首した犯人が、あの職質で引っかかった男と知り、青島が驚く。この辺り、古今東西のドラマのセオリー “Wストーリー” である。即ち、大きな話(本店が扱う大きな事件)と小さな話(ショカツが扱う小さな事件)が並行して進み、両者は一見、関係がないように見えるが、物語が進むにつれ接近して、交わる。そして小さな事件のほうに、大きな事件を解く重要な鍵がある。『踊る』シリーズは基本、このフォーマットで作られていると言っていい。
映像と音楽だけでお茶の間に語られるドラマの力
そして―― 伝説の第10話である。真下(ユースケ・サンタマリア)が、雪乃(水野美紀)の目の前で撃たれ、救急搬送される。それを知らされた湾岸署の署員たちはいつものお気楽さが消え、空気が一変する。仲間が撃たれたのだ。緊急配備にあたり、拳銃携帯命令が発令される。保管庫の前に整列し、自身のプレートを置いて、銃を手に取る署員たち。ここの描写がやたらカッコいい。君塚サン曰く「現実にあんなシーンは存在しないが、普段は銃を持たない彼らが銃を持つことの重要性を描くのに必要なシーン」と。これを “あたかもリアリティ” と言うらしい。
で、クライマックスだ。雨の中、湾岸署の署員たちは、懸命に検問にあたる。本当は、撃たれた仲間のために犯人を捜査したいのかもしれないが、ショカツにできる仕事は、検問なのだ。だが、それも犯人を検挙するための大事な仕事。ここに至り、視聴者も先の和久さんの言葉を思い出す。「犯人に手錠をかけるのは上の者がやればいい。俺たちは犯人を追う兵隊なんだ。それでいい」――。
このシーンは泣ける。バックにかかるのは、先にも書いたように、主題歌をアレンジした「Love Somebody(Jesus Version)」。この3ヶ月間、『踊る大捜査線』という物語が伝えたかったものが、映像と音楽だけでお茶の間に語られる。これぞ、ドラマの力である。
ちなみに、この第10話の演出を担当したのは、本広監督ではなく、セカンドの澤田鎌作サン。本店とショカツじゃないが、セカンドディレクターが大きな仕事をするところも、実に『踊る』っぽい。
そして、真下警部は殉職しない。
アナタにおすすめのコラム
2024.03.11
Information
あなた
























